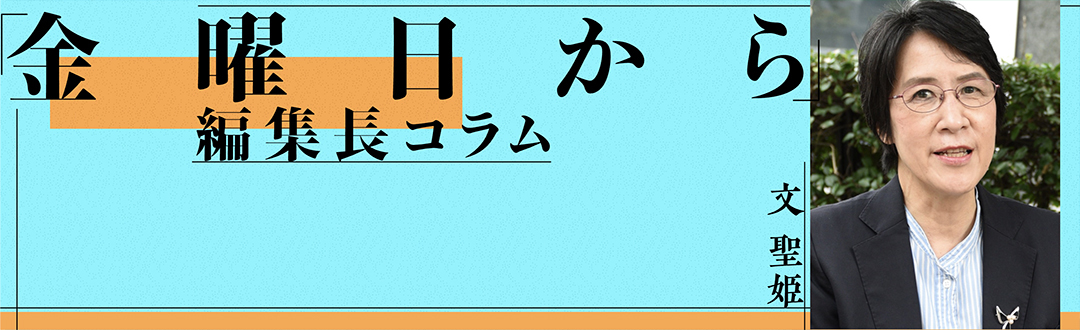活字に落とし込んで初めて、真実は社会の中に立ち上ってくる
2009年11月6日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
杖をついた高齢の女性が電車にはねられた――。警察の広報を受け、ある記者は女性を「事故の被害者」ととらえ記事にする。別の記者は「女性が”何か”によって命を奪われた」のではないかと疑念を抱く。踏切の開閉時間はどうだったのか、周囲にいる人たちはなぜ助けなかったのか――。とにかく、現場に走る。
踏切自体に瑕疵があれば、「加害者」は鉄道会社ということになる。女性が危険な目にあっているのに、そこに居合わせた人たちが傍観者のままだったのなら、「社会」に命を奪われたと言えるかもしれない。いずれにしても、現場で取材した記者と、机の上で書いた記者の記事は、まったく異質のものとなる。
新聞記者時代、こうした事例は数え切れなくあった。ルポとは結局、自分の感性に引っかかったことを目や耳で確かめ、そこに潜む真実を文章にする、そしてその意味を多くの人に伝えるという作業なのだろう。活字に落とし込んで初めて、真実は社会の中に立ち上ってくる。これこそルポの醍醐味である。
『週刊金曜日』を創設した本多勝一氏は、『朝日新聞』の有名記者であるとともに、多くのジャーナリストが憧れと畏怖の念を抱くルポライターだった。もちろん、私にとっても「どうやったって追いつけない」存在だった。本多氏はかねてから、昨今の新聞を憂えている。まっとうなルポルタージュがすっかり姿を消してしまい、歯がゆくて仕方ないのだ。本誌今週号に再録した本多氏のルポは、いまの新聞には到底、望めない。
新聞から濃密なルポが消えた理由はさまざまだ。記者の数が減り長期間の取材をする余裕がない、経営状況の悪化でカネ(取材費)のかかるルポは敬遠されがち。新聞記者がルポへの情熱を失っている……。これらは雑誌にも共通する。さらに、情熱のあるフリーランスは、発表したくても媒体がなく取材費用がまかなえない。やむなく適当な取材でお茶を濁せば、読者の評価は得られるはずもなく、結果としてますますルポは輝きを失う。
16周年記念の今週号、あえて「ルポの時代」を打ち出した。「真実を社会の中に立ち上らせる」ルポはいまこそ求められている。だが衰退の一途を辿っている。それは私たちの責任でもあると考えるからだ。正直、濃密なルポを次々に繰り出すには、編集部としても企業としても「体力」が必要となる。なかなかしんどい。どこまでできるかわからない。しかし、ルポをつくりだすうえで欠かせない、情熱と意志は持ち合わせている。真実と事実だけを伝える雑誌として、いまいちど、背筋をぴんと伸ばしたい。(北村肇)