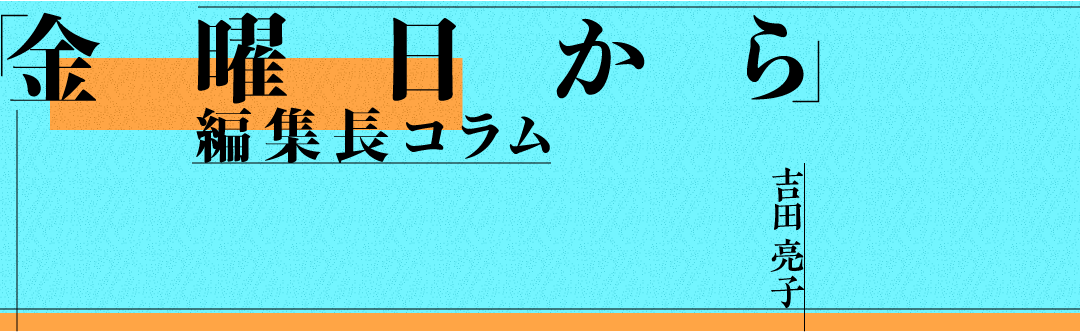イラク攻撃
2025年6月27日7:00AM|カテゴリー:編集長後記|admin
6月22日、米国がイランの核施設を攻撃した。2003年のイラク侵攻のときでさえ、公式には大量破壊兵器の隠蔽が国連決議違反だとされたが、今回は何の根拠も示されていない。イラクでは結局、大量破壊兵器は確認されなかった。今回も早尾貴紀さんが書いているように、米国の国家情報長官はイランの核兵器製造はないと報告している。
米国は1964年、共産主義勢力の拡大を恐れ、北ベトナムを挑発して戦争に介入していった(トンキン湾事件)。そして戦争に敗れ、その後米国社会は大きな負の遺産を背負うことになった。この事実を忘れてしまったのか。
今年も沖縄戦から80年の「慰霊の日」を迎え、早朝から遺族らが祈る様子が報じられた。歴史を忘れるということは同じことをくり返すのだと、米国が示している。なお今号は「2025年参院選」特集もあったため、「沖縄の記憶を継ぐ」後半は次号で掲載する。(吉田亮子)