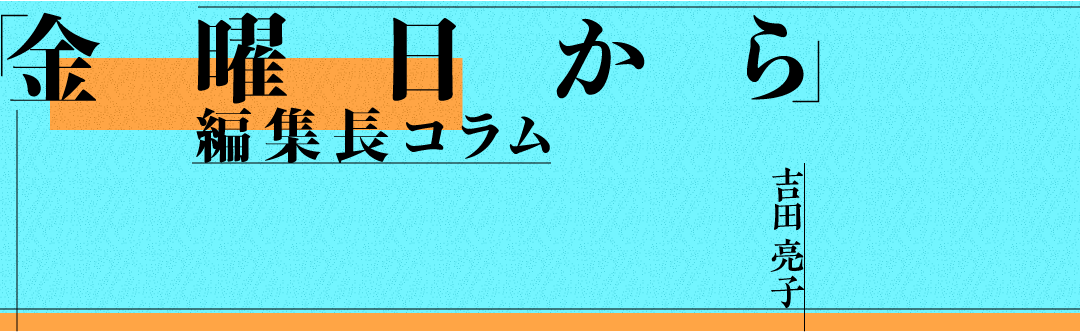高校授業料の無償化
2025年2月28日7:00AM|カテゴリー:一筆不乱|admin
日本維新の会が求めている高校授業料の無償化。現在国は年収910万円未満世帯の高校生に上限11万8800円(年間)、私立高校は年収590万円未満世帯に上限39万6000円を支援しているが、この所得制限を私立ともに撤廃し、支援金の上限を引き上げようというものだ。
しかし歓迎の声があがる一方で、実現すれば私立高校や塾が値上げしてかえって教育格差が拡大するのではないかとか、私立に集中して公立の定員割れを招くのではなどと言われ、先行して独自に実施している東京都や大阪府の状況をあえて無視した政策ではないかと反対の声も目立つ。
なにより気になるのは、カネを出すなら口も出すと、私立学校の中身に国が介入・監視してくるのではないかということ。たとえば3月の卒業式、「日の丸・君が代」が強制されないことを願う。そして、現在排除されている朝鮮学校を対象とせずになにが無償化かと。高校生まで政治の駆け引きの道具にするなということも言っておきたい。(吉田亮子)