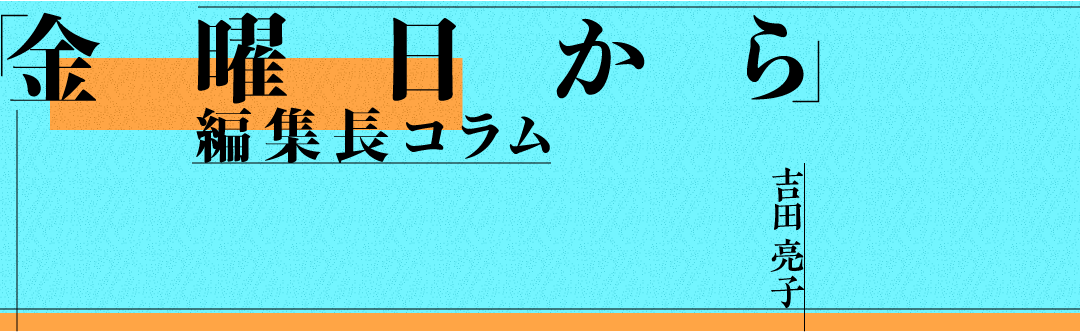暉峻淑子さん
2025年4月25日7:00AM|カテゴリー:編集長後記|admin
「希望を抱けるところは、格差をなくすとか、差別をなくすとか、そういう草の根の動きが社会に広がっていくということでしょうか?」(20頁)との竪場勝司さんの質問に、暉峻淑子さんは「そういうことを仕方なくではなく、本気でやっている人間はちゃんといる」「社会はより良い方向に変えられるという、もう一つの思想の価値体系を事実を通して見つける」と話した。続けて「『週刊金曜日』もそれをめげずにやっている人たち(の集まり)だなと思っています」と。そうありたいと励まされた取材だった。
「もう一つの思想の価値体系」を提示すべく、女性九条の会(https://x.gd/UGHZt)は講演会「尊厳を持って歳を重ねるために 福祉後退社会のなかで」を開催。講師の宮子あずささんは看護師で、『東京新聞』でコラムを担当するなど著述業も。4月28日(月)14時、東京・ココネリホール(西武池袋線・大江戸線「練馬駅」)で。(吉田亮子)