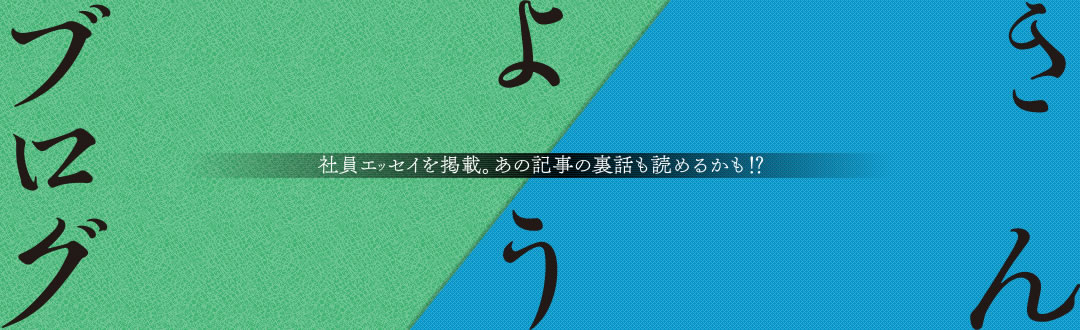本当は恐ろしい『源氏物語』(2)
2008年12月25日4:58PM|カテゴリー:そぞろ歩きはナンパ|madao
3つ目は、「女」の「男」に対する仕掛け。
最近、『源氏物語』の現代語訳刊行を始めたばかりの大塚ひかりは、『源氏の男はみんなサイテー』(ちくま文庫)で、登場する男たちを、光源氏を筆頭にひとり残らずぶった斬っていて、快哉を叫ぶ女性も多いとか。しかしこれ、元はと言えば、作者の紫式部自身がどの男をもサイテーに書いているということ。そんな男たちのモデルは、時の最高権力者・藤原道長をはじめ、宮廷や地方任官時代に出会った人たちだろうが、描き分けがあまりに見事なため、読者は自分の周囲に似たようなやついるよなー、と、それぞれの男たちのたどる情けない末路に胸のすく思いがするらしい。
象徴的な例が、最終巻「夢の浮橋」のエンディングで宇治十帖の主人公といわれる薫の君(表向き光源氏の息子だが、実は別の男性の子)が吐く「人のかくしすゑたるにやあらむ」という台詞。自分の前から蒸発した女(浮舟)をようやく見つけ出したにも関わらず、戻る気配のないことについて、「誰か(別の)男が隠し住まわせているのかと」(瀬戸内寂聴訳)考えた、というのだ。実際には、女は男という男に絶望して、自殺未遂の果てに出家の道を選んでいるのだが、それがわからぬ男の考えることは、結局こんな卑しい想像だけというもの。大長編『源氏物語』全54帖の掉尾を飾る主人公の台詞がよりにもよってこんなものなのかというわけで、『源氏物語』未完成説とか、複数作者説(歌人・折口信夫や国文学者・大野晋など)まであるのだが、いまはほぼ否定されている。だいたい複数作者説というのは、「女ひとりでこんな傑作が書けるわけがない。だれか男の作家がバックにいるに違いない」というこの薫の台詞のような女性差別的な発想に基づいているのだ。
けだし、第三の仕掛けとは、光源氏の物語が、男たちが女の好みをあれこれ論じる有名な「雨夜の品定め」で幕を明けながら、読み終わってみると、品定めされていたのは、実は、読者も含めた男たち自身だったという仕掛けである。
とまれ、そんな『源氏物語』を読んでカタルシスを味わう女性たちが、千年の間にいったい何千万、いや何億人、何十億人いたのか。
今も、全国あちこち(いや今や世界)で開かれている『源氏物語』のカルチャー講座や読書会に集まる女性たちの間で、サイテーな男たちの意見交換がささやかれているだろう。
女の男への、千年のときを超えた文字を通しての復讐劇、恐るべし。
(まだお)