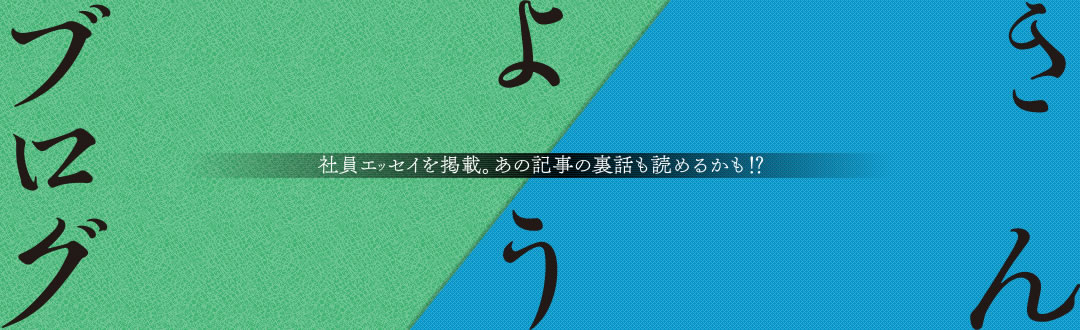最高裁の風景~傍聴記(1)
2009年2月24日6:59PM|カテゴリー:シジフォスの希望|Kataoka
シジフォスの希望(26)
午後2時前に南門前に着くと、すでに傍聴整理券を手に入れるための行列ができていた。1998年7月25日に発生した「和歌山カレー事件」の最高裁上告審。2度の「死刑判決」には重大な憲法違反と事実誤認があるとして、林眞須美被告(47歳)側が上告していた。上告(2005年6月28日)から3年と8カ月。この日(2009年2月24日)、最高裁が長く重い扉を開いた。
後尾に並ぶと、間もなく係官らしき50歳代の男性職員がアナウンス。
「午後2時から整理券を配布します」
整理券を入手したからといって、傍聴席が確保されるわけではない。抽選という〝民主的な〟手続きが待っている。さらにアナウンス。
「傍聴席は全部で34席。それ以上の場合はパソコンで抽選します」
配布された整理券を見ると、「18番」だった。じつはこのとき、配布した係官がちょっとしたミスをした。私よりあとに来た男性に、私が本来手にするはずの整理券を先に渡してしまった。その男性は私の次に列に並んだのだが、私の横にいたために、男性がもらった整理券は「17番」。これがのちに当否を分けた。
行列には続々と人が加わり、「43人」「54人」「62人」とアナウンスされるたびに増え、午後2時10分の締め切り時には「65人」に。倍率は約2倍だ。「編集から5人来たから」と列の中から女性の声。要するに、傍聴券を手に入れるために人員を投入したのだ。こちらは1人。単独である。『週刊金曜日』は5人も並ばせる人的な余裕がない。〈なんだ、最初から不平等じゃないか〉とつぶやく。
やがて、パソコンで抽選。ホワイトボードに「当選番号」が次々と貼り出されていく。「……16、18、22……」。17番をもらっていたら「はずれ」だった。係官のミスに〝感謝〟しながら傍聴券を手にする。傍聴券は指定席で、「は-4」。階段を上り、最高裁の建物内へ。
「携帯電話を切って、荷物はロッカーに入れてください。持ち込めるのは貴重品とメモ程度です」
金属探知機をくぐって、女性職員の先導で重々しい石の壁に囲まれた階段を上る。案内された場所は「第三小法廷」。なだらかなドーム型の高い天井のある部屋だ。前方の一段と高い位置に並ぶ5つの背の高い革張りの椅子。それに向かって、茶色の布張りの狭く背の低い椅子が扇状に。どちらが裁判官で、どちらが納税者の座る場所かは説明するまでもない。私は前から2列目に腰を下ろした。
やがて、5人の裁判官が入廷し、6台の報道ビデオカメラが約2分間、その様子を撮影する。テレビなどで使われるお馴染みの映像だ。中央の眼鏡をかけた裁判長が「開廷します」と宣言し、いよいよ口頭弁論が始まった。予定どおり午後3時。裁判長はまず、弁護人側に弁論を求めるが、「その前に」と安田好弘弁護人が言葉を差し挟む。弁護人側が提出した「事実取り調べ請求」はどうなっているのか、という質問である。裁判長は即座にこれを却下。これに対して、本誌2月13日号に登場した高見秀一弁護人が異議を唱える。
「1審、2審ともに死刑という重大な事件です。被害者とされる林健治さんは亜ヒ酸を自ら飲んだと証言している。最高裁は事実取り調べの義務がある」
これに対し、最高裁は即座に検察側に意見を求めた。「検察官のご意見は?」。
弁護団5人に対して、1人だけ出廷した検察官は、「弁護側の請求には理由がなく、直ちに棄却を求めます」とひと言。すると、裁判長も即座に「異議申し立てを棄却します」。どう「理由」がないのかの説明もせず、「棄却」の理由も述べずに、にべもなく一方的に退けるあたり、さすが「法の番人」である最高裁だ。
(つづく) (2009年2月24日・片岡伸行)