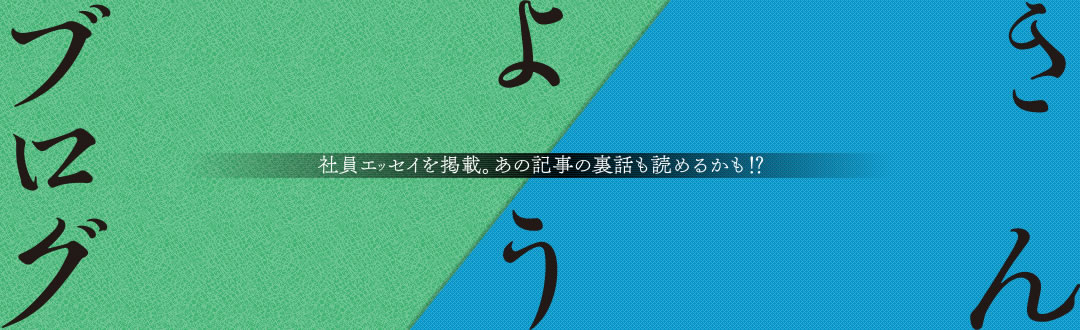新聞記者本の変遷
2008年2月15日9:00AM|カテゴリー:風に吹かれて|伊田浩之
前回のコラム(2月8日付)で、1987年5月3日に起きた朝日新聞阪神支局の襲撃事件にふれ、「いまから考えると、確かにこの事件が一つの転機になったような気がしてならない」と書いた。「この事件以後、何がどのように変わったとお考えでしょうか」と読者からメールをいただいた。回答の一助として、手元にある新聞記者が書いた本(新聞記者を辞めてから書いた本を含む)のタイトルを発行順に書いてみよう。
『ドキュメント新聞記者』(読売新聞大阪社会部著、講談社、1980年)
『事実が私を鍛える』(斎藤茂男著、太郎次郎社、1981年)
『職業としてのジャーナリスト』(本多勝一著、朝日文庫、1984年)
『新聞記者の現場』(黒田清著、講談社現代新書、1985年)
『警察(サツ)回り』(本田靖春著、新潮社、1986年)
★1987年5月3日 朝日新聞阪神支局襲撃事件
『新聞記者の仕事とは 支局襲撃事件の衝撃』(岩波ブックレット、1987年6月)
『新聞が衰退するとき』(黒田清著、文藝春秋、1987年8月)
『新聞記者が危ない』(大谷明宏著、朝日ソノラマ、1987年8月)
『新聞記者の処世術』(原寿雄著、晩聲社、1987年11月)
『それでも君はジャ-ナリストになるか』(原寿雄著、晩聲社、1990年1月)
『新聞記者を取材した』(斎藤茂男著、岩波書店、1992年)
『滅びゆくジャーナリズム』(本多勝一著、朝日文庫、1996年)
『新聞記者をやめたくなったときの本』(北村肇編著、現代人文社、2001年)
ちなみに最後の本の編著者は、発行当時は毎日新聞社で働いていた、『週刊金曜日』の現編集長。「この本を読んで辞めた新聞記者はいない」と豪語している。
すべての本を網羅しているわけではもちろんないが、上記のタイトルから傾向が浮かびあがる。事件以前の本は、「新聞記者は大変でつらいけれど、やりがいがある仕事だ」と訴えるものが多かった。それが次第に現状に警鐘を鳴らす本が増える。しかも、現役よりも、かつての自由な雰囲気を知っているOBに危機感が強い。
読売新聞大阪社会部に一時代を築いた、故・黒田清さんが読売新聞の社内体質に見切りをつけて辞めたのが1987年1月。その4カ月後に襲撃事件が起きた。ただ、黒田さんの『衰退するとき』は月刊誌『文藝春秋』の連載(1987年3~5月号)が基だから、事件には触れていない。
黒田さんと一緒に読売新聞を辞めた大谷さんの『危ない』には、事件とその報道記事への怒りがあふれている。「私の心の中に居座り続ける澱(おり)のようなものは一向に消えない。特にこの事件を報道する新聞各社の紙面を見るたびに、固まりどころか、沈殿物になっていくのであった」「そこに憤怒の思いに顔を真っ赤にし、怒りで手を震わせ、そして拳を握りしめて、全身で相手にぶちあたって行くという記者の姿勢が感じられないのだ」「犯人は『記者を撃つ』ことで『言論を撃った』のである」「いま新聞記者は、休日の当直勤務の夜にわけもわからないまま惨殺され、また、あまりに巨大化したマスコミのメカニズムの中で、窒息死させられようとしている。そして社内の目を覆いたくなる粛清の嵐の中で、その精神を殺されようとしているのである」
頑張ってすばらしい仕事をしている新聞記者は今も多い。だが、増ページで多忙になったり、インターネットの普及で、(私はそうは思わないが)新聞の先行きが暗いとの見方が広がったりしたためか、なんとなく元気をなくしている記者が少なくないようにも思える。
「新聞」がタイトルに入っている書籍をインターネットで検索すると、昨年出たのは『崩壊する新聞』、『新聞社―破綻したビジネスモデル』『新聞の時代錯誤―朽ちる第四権力』などだった。自分自身の体験を含め、この話をさらに続ける。