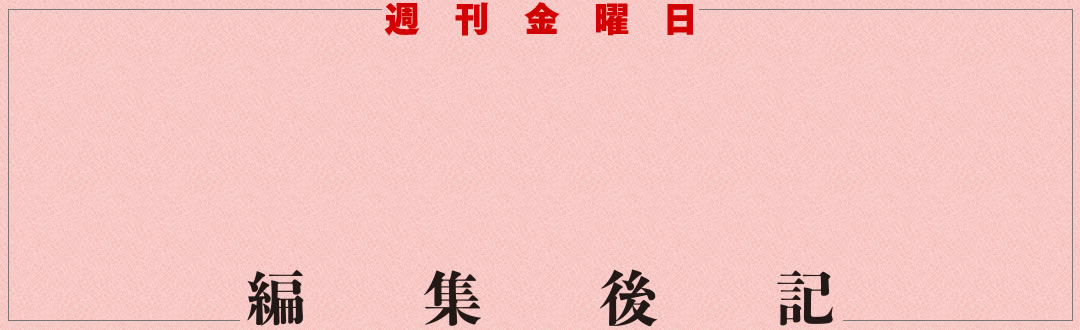744号
2009年03月27日
▼「君が代不起立」で免職の危機にある東京都の教員、根津公子さんは停職期間中、校門前「出勤」を続け、子どもたちや教員、地域の人々に対話を呼びかけてきた。不審者扱いされて警察がきたことや心ない言葉をかける人もいた。しかし校門前で語り続ける姿は、人を動かす大きな力となった。
今回対談した崔善愛さんも、二〇〇五年に校門前で根津さんと出会った。校門前からは母親の会ができたり、一緒に「出勤」する教員も現れた。「双六」を作った壱花花さんも昨年、新聞の意見広告にイラストを描いたのがきっかけで、今は強力な協力者だ。出会いが大きな支援の輪になりつつある。
根津さんの勤務校の卒業式は二四日。しかし、終わる前から都教委は、翌二五日に事情聴取を行なうと言ってきた。処分発令日は三一日。通常は研修センターで伝えられるが、根津さんについては昨年、勤務校に職員が突然やってきた。今年もどうなるかはわからない。が、「君が代」処分にNOを私も言い続ける。(吉田亮子)
▼働き始めて一カ月がたつ。
向かいのデスクはNさん。膨大な資料に埋もれながらひたすら読んで書いて。頭をかきかき、舌打ちしながら読んで書いて。時にバナナでエネルギー補給しながら、読んで書いてしている。
左を向けば六人の校正さん。点や丸、カギ括弧の位置から文字の配列まで、読者が気持ちよく読めるよう言葉の隅々まで配慮を行き渡らせる。蛍光灯の下、一字一句丹念に文字を追っていくその様は、世の空気に抗いながら夜なべで内職をする戦時中のお母さんとお父さんを思わせる。自分で何度もチェックし、揚々と出した原稿も、校正さんの手にかかれば次々にミスが浮かび上がる。世に出るための「最後の門番」、その壁はとても高く、熱い。
文字通りの十人十色だが、一人ひとりの想いが『週刊金曜日』という形になる。三月より「市民運動案内板」を担当しています。行き届かないことが多々ありますが宜しくご鞭撻下さい。(野中大樹)
▼先週末、三週間ぶりに市民農園に行った。雨が降ったり、予定がはいったり、なかなか作業ができなかった。が、さすがに畑がたいへんなことになるので、気合いを入れて雨の中、向かった。
畑に向かうと、いろんな区画で黄色い菜の花が咲いた。春だ。菜の花のからし和えが好きなので、うちも植えればよかったな。と、よく見ればわが畑でこんもりと咲いている。残念ながら、かつての白菜たちだった。白菜や大根などのアブラナ科は収穫せずにいると菜の花のような黄色い花を咲かせていく。クレソンも咲いていた。負けおしみではないが、畑をやっている贅沢の一つはこのように野菜のいろいろな顔を眺められることだ。とはいえ、隣に植えていた一〇本ほどの大根はすかさず全部抜いた。よい出来だった。
最近はギャル米だのと、ちょっとした農業ブームだ。批判もあるがいい傾向だ。来年は市民農園の契約期間が切れる。ブームが続いていれば申し込みの抽選倍率が高くなる。痛しかゆし。(平井康嗣)
▼母が引越したので、届などを出すのに付き合う。近頃本人確認がうるさいのははなから承知。(母は孫の預金を作ろうとして既に銀行に断られている。)面倒がる母と二人、一緒に各所をまわった。
役所で健康保険証を出すと、「他に何かありませんか?」診察券や銀行のカードが要るらしい。転出証明の他にまだ要る? 顔写真のあるものと言うが、運転免許証はない。つつましく暮らした昭和ヒト桁でパスポートもない。最近はそういう人に写真入り住民基本台帳カードが人気らしい。
小さい枠に、さらに小さいその枠に書く内容を示す文字。結局「ここに名前」「ここに住所。違う違う、こっちの住所!」といっても新しい住所は頭に入っていないので指さしながら口述筆記。
何軒かまわるうちに、母も私も同じことを思った。「これだったら、本人じゃなくてもいいんじゃない?」「『貸し老人』とか?」「きっと流行るよ」「そしたら私がしようかな」あれれ疲れているんじゃなかったっけ?(志水邦江)