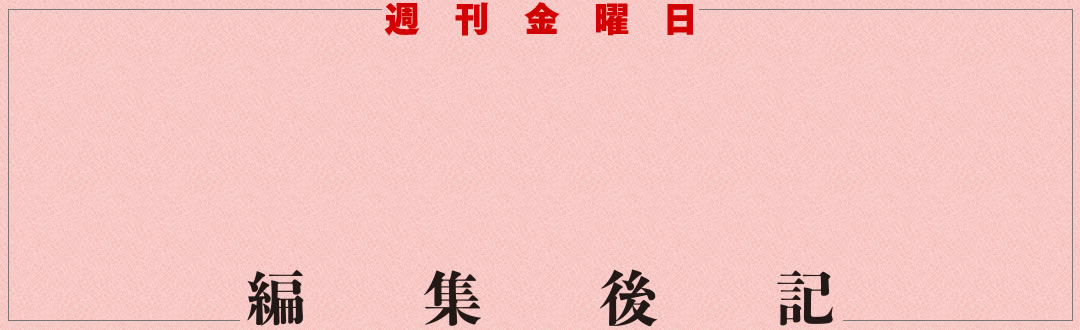743号
2009年03月20日
▼以前から、かなりのファンであるふたりの人間が、エルサレムとハリウッドで、ほぼ同時期に「受賞スピーチ」なるものをした。
エルサレム賞の村上春樹と、『ミルク』でアカデミー賞主演男優賞のショーン・ペンである。距離は離れているが、ふたりのしゃべったことの本質は同じだった。
壁と卵のたとえで、壁を「(政治)システム」とするなら壁にあたって割れる卵の側に常に立つとする村上と、授賞式会場の外で同性婚に反対するプラカードを持つ人達に「自分の行ないを改めてくれ。子孫の代まで続く恥だ」「すべての人間は平等だ」と言い切ったショーン・ペンが僕の中では共鳴した。
イスラエルに行き、「その場所」で言葉を発することが文学者の役目と考えた村上の見解は『文藝春秋』の四月号で読める。ゲイであることを公言し、一九七八年に同僚議員により射殺された『ミルク』の実在の主人公、ハーヴェイ・ミルクは八四年に『ハーヴェイ・ミルク』として映画化。DVDでも見られます。(土井伸一郎)
▼言わずとしれた保守系月刊誌、『諸君!』(文藝春秋)が五月発売号で休刊する。部数が六万数千部にまで落ち込んだとのこと。『金曜日』の約二倍の発行部数で休刊とはせつないが、文春さんにも事情があるのでしょう。論調の異なる雑誌ではあったが、選択肢がひとつ減ることは、読者と先の見えない出版業界にとって不幸なこと。『論座』、『月刊現代』とリベラル誌の休刊が続くなか、書店の棚がますます寂しい。そしていま、言論のありようから紙媒体の行く末までの思いを馳せている。
本誌の書店実売率も二月から低迷中。消化率五割以下では、店頭での生き残りは困難だ。もちろん『金曜日』の主体は定期購読者に支えられた直販雑誌。だが、あえて考えたい。志の近い仲間に囲まれているせいか、心地よい言説ばかりに目が向いていないか? 言葉は読者に届いているのか? しばらくは、試みと失敗を繰り返しながら、世に問う作業を続けていきたい。今年から販売部門の責任者を務めています。 (町田明穂)
▼身の回りで最近発見したことをいくつか。昨年ベランダのハチに植えたレモングラスがなんとか冬を越したこと。以前は枯れちゃったのに、暖かい日が続いたんですねえ。自転車で夜帰宅する途中、道路の掘り返し工事がぼちぼち出てきたこと。三月なんですねえ。
知り合いのライターさんが住むマンションは家主が国会議員。昨年、選挙近しと喧伝されていた時、家主多忙につき、散歩の回数が激減した飼い犬がストレスたまりまくっているという話をきいていた。久々に近況をきいたところ、そのワンちゃんは「選挙区に送られたようで、ずーっと静かです」とのこと。そろそろですかねえ。
小学一年生の娘のランドセルから〇点の答案用紙が出てきたこと。のび太と一緒なんですかねえ。児童館で毎日『ドラえもん』を読んでますから。
社内で机の大移動を行なった時、机の上に積んだ本の山の向こうとこっちから、なくなったと諦めていたメガネが二個ほど。……(小林和子)
▼宣伝めいて恐縮だが、拙著の『オバマの危険』を読んだ知人から、「要するにオバマでは希望がないわけだ」と言われた。咄嗟に「そうだ」と返答できなかったのは、オバマの評価とは別に「希望がない」という表現自体を心のどこかで忌避しているからかもしれない。ギリシャ神話の「パンドラの箱」の逸話をひもとくまでもなく、希望こそ最後の拠り所と呼びうる。人類は奴隷制度を廃止するまでにどれだけの犠牲を払ったかは別にして、それは奴隷からの解放という希望の勝利であったはずだ。同様に戦争という行為が地上から消える時代の到来は、私たちがそれへの希望を絶やさぬことが前提となると信じたい。米国に希望があるとすれば、一指導者ではなく多くの人々のより良き社会に対する希望の抱き方にかかっていよう。検証すべきは、自身の希望に対する確信の度合いなのだ。これからも世界が先般のガザ大虐殺のような事態を再び目撃することになろうとも、怒りのペンの奥に希望への確信を忘れまい。(成澤宗男)