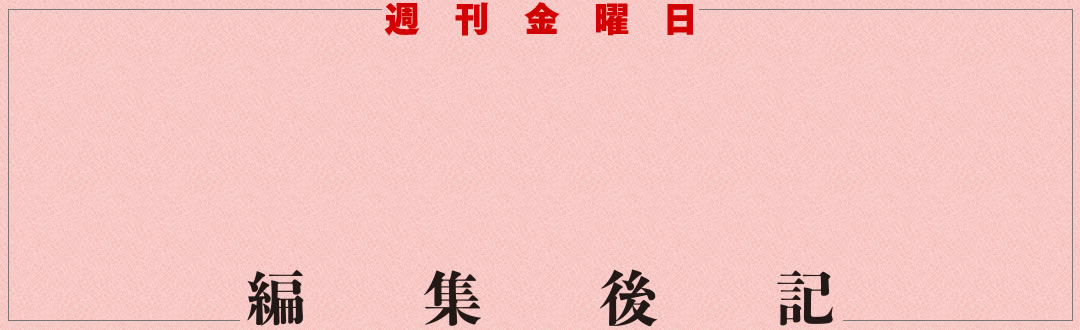745号
2009年04月03日
▼横浜国大教授の岸本重陳さんが亡くなって一〇年ということで、その「思い出」を書くことになった。「市民の経済学者」だった岸本さんは奥村宏さん、内橋克人さんと共に私にとって大事な兄貴分であり、私は本誌の「風速計」欄に「三兄の死」を書いて、六二歳での早すぎる死を惜しんだことがある。その岸本さんが、私が編集していた『VISION』に、「“お恵み”の福祉から“支えあい”の福祉へ」を発表し、それを鶴見俊輔さんが『朝日新聞』の「論壇時評」で推賞したのは一九七五年の六月だった。いわゆる「定額給付金」に私たちが違和感をぬぐえないのは、それが見当違いな「お恵み」の思想に発しているからである。それを「支えあい」に転換するにはどうしたらいいか。いろいろ知恵を絞って友人知人への本誌の購読プレゼントに使ってもらったらどうかと考えた。あるいは手前味噌に過ぎると叱られるかもしれないが、これは低劣な麻生首相と追随する公明党への有効な反撃になると思う。(佐高信)
▼昨年から金融危機が世界を覆っているが、「お金だ、セレブだ、勝ち組だと、うっとうしい世の中。これを読むとすっきりする――和田誠」と帯にある、トルストイ『人にはたくさんの土地がいるか』(北御門二郎訳、あすなろ書房)を子どもと一緒に読んでみる。自分も随分昔に読んだが、強烈な印象が今でも残っている。
巻末の年表によると、トルストイは一八七二年にヤースナヤ・ポリャーナの邸内に学校を開いた。彼は当時の自由主義者らと共に自由な教育を実践しようとした。教育の対象は、「自由な子ども」であると彼は自分の教育雑誌に書き、強制や懲罰のない学校を目指した。
こうした思想と実践が、米国の現在のフリースクールのルーツ、「モダーン・スクール」が二〇世紀初頭にスペインに誕生した背景のひとつである。米国のフリースクール関係者は自分たちがトルストイら一九世紀自由主義者の教育思想に遡ることを自覚しながら、自分たちの実践を子どもたちと未来につなげている。(樋口惠)
▼「入社する前から生意気」と評される私にも頭が上がらない人物がいる。恩師である服部孝章教授はそのひとり。常に様々な媒体で発言されている先生は、先月末にテレビ東京で放送された「TV強制合宿!?タブーな番組企画会議」にも出演されていた。
この番組は、先生に加え、木村三浩さん、たむらようこさん、中村うさぎさん、三上寛さん、森達也さんの計六名が、現在のテレビではタブーとなっているテーマを番組企画するというもの。六人それぞれの視点から出される企画は今のテレビには斬新なものばかり。
番組を見ていて、ふと気づく。そういえば、わが『週刊金曜日』はタブーなきメディアを標榜している雑誌ではないか。果たして看板にふさわしき内容を読者に提供し続けられているのか。いつも同じ切り口では、タブーができる。違った角度からも物事を捉えられているのだろうか。厳しいコメントをされる恩師の姿が目に浮かぶ。叱られるうちが花というけれど、期待には応えたい。(赤岩友香)
▼中国・四川大地震からもうじき一年。今週号で深田志穂さんの写真企画「悲しみが怒りに変わるとき」を掲載した。親より先に子どもが逝くことほど辛いことはない。ましてやそれが“天災”ではなく“人災”だとしたら……。遺影と共にカメラを見つめ、世界へ向けて“なにか”を伝えようとする親たち。一枚一枚の写真と向き合いながら泣く。ひとりひとり、地震の起こるあの日まで、たしかに“生きて”いた。みんなでご飯を食べて、泣いたり笑ったり怒ったりといった、どこにでもあるような家族の風景が消えた。
日曜の朝、桜は咲いたかとか、車がないから高速道路が安くても関係ないとか、たわいない話をしながら遅めの朝食をとる。金を使わないものは人間扱いされない世界の中で「もしすべての住居の家賃が〇円だったら……」「学校も医療も〇円だったら……」人はもっと優しくなれるのになと思う。
先週末、本誌主催の阿佐ヶ谷でのイベントで聞いた「共生」という言葉が胸に響く。(本田政昭)