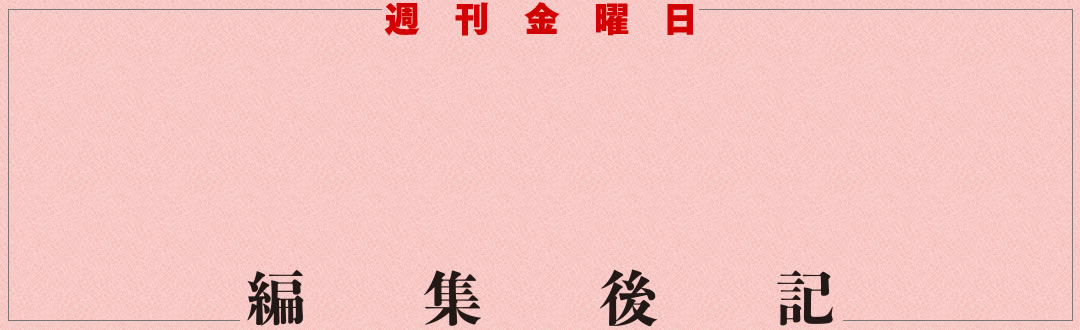734号
2009年01月16日
▼『産経』の古森義久らを典型に、都合のいい米国の論者の「ご高説」を引き合いに出し、「日本人は知らないだろう。だからダメなんだ」とばかりに自分を「米国の高み」に置いて悦に入る愚かな癖が保守派・右派の宿痾になって久しい。かつてウォール・ストリート仕立ての「金融立国」を賛美し、「早く日本も続くべきだ」と唱えていた竹中平蔵や野口悠紀雄あたりも同病なのだろう。この連中は、自身が熱を上げた「市場原理主義」ならぬ米国崇拝熱が極まった「米国流原理主義」の徒だ。原理主義の怖さは一見論理的な装いを凝らしながら、本質は情緒(又は感情的傾倒)にあるため現実とのフィードバックが効かない点にある。だから金融で「BIS規制だ」「ビッグバンだ」と脅しを真に受けて経済をガタガタにされながら、この連中は馬耳東風なのだ。嘆くべきはこうした原理主義者を野放しにしているマスメディアだが、金融危機の元凶であるルービンやサマーズ、ガイトナー一派に対する最近のヨイショ報道に接するにつけ、彼らも実は同病なのではないかと案じてしまう。(成澤宗男)
▼『セブン-イレブンの正体』が売れている。発売ひと月足らずで重版三刷りだ。潜入ルポまで行ない、一般消費者の知らない「流通覇者の実像」に迫ったこの作品は、本誌の好評連載で、掲載号の実売率は常に高かった。だから売れるのは当然か――。実は本書、当初一部の書店で扱いがなかったのだ。
発売前、ある取次会社から新刊委託に際して「指定配本以外にパターン配本することは難しい」との連絡を受け、担当者と窓口に赴いた。理由を尋ねると「取締役の不利益になることはできない」とのこと。取次会社の役員に関する記述が引っかかるらしい。数度のやり取りの後、「現場の判断で、誤解を受けることをしてしまった。ついては再委託をしたい」との謝罪回答を受け、晴れて本書は全国発売となった次第だ。そして、この間の模様がネット上に流れ、話題となり売上に繋がった。
「言論弾圧」事件ともみて取れるが、取次店にその認識はなかったろうし、近しい出版社に話しても「よくこんな本出せたね!」と感心されるだけ。これが〇九年の出版の現状。哀しい。(町田明穂)
▼チャップリンの『モダン・タイムス』を観た。機械化された工場で、まるで部品となって働くチャーリー。彼は精神を病んでしまう。彼から奪われた身体性が、彼の精神をも、奪ってしまったのだ。
「知的といわれるものを、学者さんは頭脳でしか育たないと思ってるようだけれど、上等な知は、手や体を通して育つ。そのほうが本物じゃないかなあ。」(小関智宏著『現場で生まれた100のことば』早川書房より)。元旋盤工であり作家の小関さんがものづくりの現場で出会ったことばの一つ。
頭ばかりで考えていると、いつの間にか、身体がガチガチになっている。気づかずに放っておくと、今度は、身体の動かし方がわからなくなってくる。こういう生業(おそらく知的産業の部類に含まれる)に就いたからこそ、まずは手を動かし、体を動かし、自分の身体に耳を傾けていきたいと思う。(ゆげたりえ)
▼指紋押捺を拒否してアメリカに留学し、再入国の不許可取り消しを求めて国と裁判で闘った在日三世のピアニスト、崔善愛(チェソンエ)さんが、『父とショパン』(影書房)を出版した。中身については別の機会にして、ここでは一一日に行なわれた出版記念パーティーのことを少し紹介したい。
会場となったのは東京芸術劇場の会議室。ここは国の施設らしく規制が多くて、何かとうるさかったという。まず飲食禁止だと言うので交渉すると、軽食ならOKとなった。グランドピアノが置いてあるので使用を申し出ると、本格的な音楽を弾いてはいけないがBGM程度ならOKだという。崔さんは、どこへ行っても国と闘わなければならないと苦笑する。
いちいちこだわって生きるのはなんと疲れることか。日常の「なぜ?」を流してしまうのは簡単だが、それでは大きな「なぜ?」と闘うことはできない。(吉田亮子)