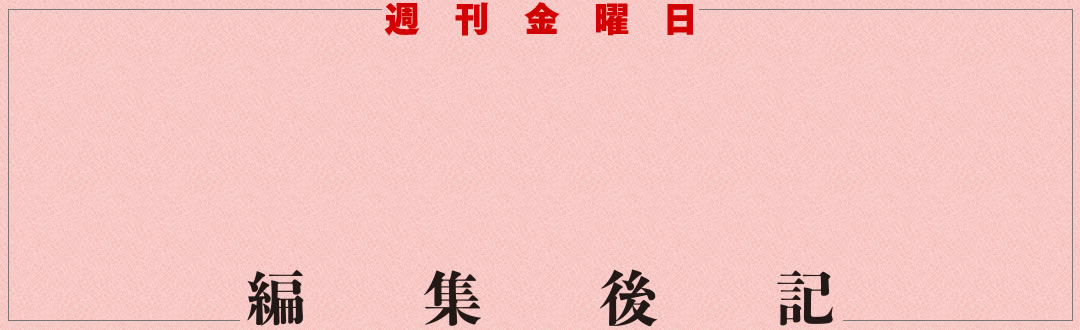733号
2009年01月09日
▼二〇〇九年最初のこの号から、法政大学教授の田中優子さん、弁護士の宇都宮健児さん、そして、北海道大学准教授の中島岳志さんに編集委員に加わってもらった。三人の中で一番読者になじみの深いのは田中さんかもしれない。昨秋の「水俣紀行」の前にも、死刑問題や石原慎太郎批判に登場してもらっている。専門の江戸研究以上に現代への洞察がシャープだと思うのは私だけだろうか。
田中さんと宇都宮さんに編集委員をお願いする前に、共に藤沢周平ファンの二人に私が司会として加わって、藤沢文学の魅力を語った。多分、読者はそこで、東大法学部卒のエリートでありながら、弁護士になって屈折多い人生を送ってきた宇都宮健児の人柄に惹かれたことだろう。現在、宇都宮さんは「反貧困ネットワーク」の代表である。ちなみに副代表が雨宮処凛さん。その雨宮さんと同い年なのが、中島岳志さんで、中島さんは『中村屋のボース』(白水社)で大佛次郎論壇賞を受けた。
今週号では田中さんが自己紹介がわりに「風速計」を書き、二三日号で宇都宮さんには北村肇編集長がインタビューをする。そして、中島さんについては、私が“他己紹介” 的に「抵抗人名録」に取り上げた。若い人だけではなく、内橋克人さんにも編集委員に加わってほしいと落合恵子さんや私がお願いしたが、病後の体調に自信がないからと辞退された。編集委員には本誌にいろいろと刺激を与えてほしいと思っている。(佐高信)
▼年末、以前在籍していた会社の先輩が退職するとの報せを受け、送別会会場に向かった。齢五〇代半ば、次の仕事は決まっていない。
中小企業の実務を指南する直販雑誌と、ビジネス書籍を発行するこの出版社の社員は「働き盛り」と呼ばれる年齢で退社することが多く、近く創業六〇年を迎える老舗だが、定年退職日を迎える人は稀。いわゆる「肩たたき」。自己都合の体裁で皆少しずつ辞めていく。
二次会の途中から参加。宴は和やかに進行している。当人含め参加者の表情が一様に明るいのが、悲しい。酒の力もあって、徐々に腹が立ってきた。仕方ないと諦めているのか――俺も在職中、何もできなかったじゃないか――そんな葛藤を抱えつつ、部外者が宴席のシメに声を荒らげるのは野暮の極み。「ニコニコしているだけじゃあ、駄目なんだよ!」と胸の奥で呟くだけだった。(町田明穂)
▼〇六年年始号の本欄に入社あいさつを書いてからちょうど三年が経った。当時の文を読み返してみると、「市民が互いを監視し、牽制し合わなくてもよい社会を築いていくためにはどうしたらいいか」、その答えに近づきたいと書いていた。購読していた雑誌の編集部にきて、気負ってガチガチになっている様子を思い出すと恥ずかしいけれど(いまも基本的には変わっていないような)、書いた思いはそのまま抱えている。
ただ、「市民が」という主語ではなく、「私が」という主語でいろんなことを考えることが多くなった。自分はこれから本当に何を大事にして生きていきたいのか。どんな時代でも、変わらず大切にしていきたいものは何なのか。日々の生活のなかで意識することが多い。頭の血管や筋肉がこわばってガチガチにならないようにしながらも、考え続けたいと思う。(山口舞子)
▼昨年に続き、東京・上野と山谷(台東区)の越冬闘争に参加した。野菜や肉を一緒に切り、煮炊きする共同炊事だけの参加だが、共に食すときの温かさは身に沁みた。
前々日に、日比谷公園で「年越し派遣村」を運営する労組のメンバーが、炊き出しのノウハウを教わるために山谷を訪れたという。「ルン・プロと呼ばれた私たちが労組に何かを教えるなど考えられなかったこと」とは、支援者の言。仕事と住処を同時に失う「派遣切り」が断行される残酷な年末が、逆に新しい動きにつながっている。
だが、派遣村村長・湯浅誠さん(本誌新編集委員の宇都宮健児さんが “名誉村長”)が「岩盤」(一六ページ)と呼ぶ、この国の既得権益構造の壁はまだまだ厚い。一層深刻化する「労働/生存」問題、〇九年も追及し続けたいと思います。本年もよろしくお願いします。(山村清二)