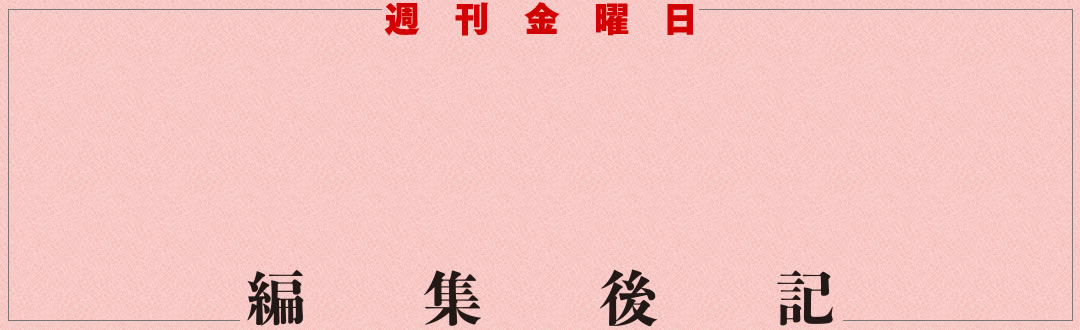732号
2008年12月19日
▼「これ、面白いから読んでみろよ!」約一二年前、兄から手渡された一つの雑誌。初めて読んだときの衝撃は今でも鮮やかに甦る。その雑誌が自宅に届く金曜日は、学校が終わると道草もせずに帰路を急いだ。まさか自分がその出版社に勤めることになるなんて――。
今年はいろいろな “縁”を感じさせる一年だった。
一方、この一年も多くの月刊誌や週刊誌が休刊に追い込まれた。グーテンベルク以来の技術革新、価値観の多様化、世界恐慌の危機。様々な変化に取り囲まれ、出版業界は衰退の一途を辿るばかりなのかもしれない。「雑誌が休刊となるときは、時代の中でその役割を終えることを意味する」と言う人もいる。仮に雑誌に役割があるのだとすれば、『週刊金曜日』の役割とは何だろうか。果たすべきことは、まだあるはずだ。決意を新たに二〇〇九年を迎えたい。(赤岩友香)
▼「マルクスが生きていたら今の世の中をどうみるだろうか。誰かそれを書ける人はいないだろうか」という発言が、会議の自由討論で出ました。私は即座に佐藤優さんなら可能だろうと考えました。
佐藤さんの本に次の記述があるからです。<私の記憶は映像方式で、何かきっかけがあるとその映像の中の人物が動き出し、話し出すので、本を読む場合にもその方法で記憶を定着させる。(中略)資本の原始的蓄積に関する部分ではマルクスが資本主義体制の「最後の警鐘」が鳴る様子を熱っぽく語る映像が見える>(『国家と神とマルクス』角川文庫七四ページ)
佐藤さんも架空対談の依頼を面白がってくださり、今回の特集となりました。興味を持たれたらぜひ原典を読んでください。他の社会主義者を登場させる続編も企画中です。乞うご期待。(伊田浩之)
▼二〇〇五年のプロジェクト立ち上げから約三年と、協力者の方々を大変お待たせしましたが、『もうひとつのノーベル平和賞 平和を紡ぐ1000人の女性たち』をこのほど刊行しました。
「『1000PeaceWomen』を1000人で翻訳しよう」プロジェクトの詳細はURL http://www.asahi-net.or.jp/~zv6m-ishr/1000peacewomen/をご覧いただきたいのですが、翻訳者・チェッカーの公募→翻訳→チェック→監修→プロジェクトコーディネーターと私が最終チェック、という行程に加え、固有名詞の現地読み調べと差別語の排除でも時間を要しました。予想以上に大変で、もうやめてしまおうかと思いながらもやめられなかったのは、本の中の女性たちの命がけの活動に感動したことと、翻訳本に携わった方全員がボランティアという心意気に励まされたからです。重く高価な本ですが、多くの方の目に触れる場所に置いていただけることを願っています。(宮本有紀)
▼「語り歌の継承」を主宰する館野公一氏は反原発など様々な問題に題材を得、語り歌い続けている。
三〇年前、長野県須坂駅前でひとり反原発の「ガリ版刷りの新聞」を配っていた坂田静子さんとの出会いを歌った曲がある。静子さんは闘い途中で病死してしまった。が、娘の雅子さんは、ベトナム戦争に従軍した夫の急死が「枯れ葉剤」に起因していることを疑いベトナム取材を敢行。今年、ドキュメンタリー『花はどこへ行った』を完成させた。試写会に臨んだ館野氏からそのニュースが発信されていたが、今回ようやくそのDVDと出会えた。雅子さんの淡々としたナレーションに反して伝わってくるのは怒り、そして悲しみ。
怒りの渦巻くこんな時代だからこそゆえか、自分の言葉で問題を表現する「語り歌」の意義を改めて実感している。(柳百合子)