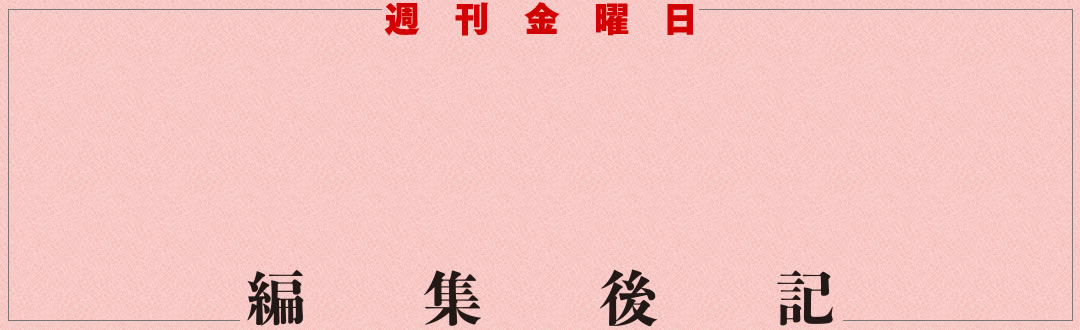730号
2008年12月05日
▼筑紫さんの企画でもっとも印象深いのは、特集でも一部紹介している「責任編集のページ」だ。まずはテーマを決め、対談の人選段階から、筑紫さんと電話であれこれ相談し、依頼していく。その過程の楽しさといったらなかった。
忘れられない言葉がある。私が入社間もない頃、対談相手にある若手ミュージシャンを提案したことがある。ただ、そのことで当初の企画意図とは少しずれる可能性があった。遠慮がちに切り出すと、
「いや、そういうのどんどん言ってよ。こっちも勉強になるから」
純粋に “知りたいんだ”という筑紫さんの貪欲さが伝わる声だった。その姿勢に若造編集者は恐縮しつつ、胸が震えるほど嬉しかった。もちろん、私の情報を筑紫さんが知らない、などということはその後、滅多になかったのだが。
本誌を本当に大切にしてくださっていたと思う。原稿や企画の依頼を、断られた覚えがあまりない。山ほどお叱りを受け、片手で足りるがお褒めの言葉をいただいたこともあった。記憶にある筑紫さんの声を大切に心にとどめ、編集に携わっていきたい。(小長光哲郎)
▼私が筑紫さんの担当をしていたのは一〇年以上も前のこと、「我自リ古ヲ作ル」のコラムタイトルを問う読者の方もまだ結構いた。
その頃は社内でゴタゴタすることもあったが、徹底して不干渉、不介入。話してみて感じたのは、人間に対してゴリゴリするタイプじゃないし、アバウトなんだな、ということ。
しかし言葉に関しては厳しかった。原稿について不用意に、疑問を呈したり、意見を述べようものなら、心臓がズキリとする言葉が返ってくる。明らかに不機嫌と思える反応。その一方で、何かしら意見が反映されてくる。適当にあしらう手もあろうに、いちいち腹を立て、そして頭を悩ましてくれる。その生真面目さが正直、嬉しかった。
「オウム」のときは別のテーマの原稿ばかり送ってくる。うちにもオウムのことで書いて、とお願いしたら「この小さなスペースで何が書けるか」ときた。でもインタビューなら、と時間をたっぷりとってくれた――。誰よりも気骨のある人だった。(小林和子)
▼赤坂小梅という歌手がいた。
「炭坑節」「黒田節」「おてもやん」「ソーラン節」と聞けば思い出す方も多いだろう。大正・昭和の激動の時代を、唄一筋に生き抜いた稀代の歌手だ。
映画『小梅姐さん』は、小梅が生まれ育った筑豊の風土や、芸者修業に明け暮れた北九州、歌手として頂点を極めた激動の東京、終の住処となった千葉県館山まで、各地にその足跡を訪ね、残された唄や映像を駆使し、関係者のインタビューなどを交えながら、唄を愛し唄に尽くした「赤坂小梅」という女の生き様を見事に描いたドキュメンタリーである。
こんな桁外れな存在感のある歌手がいたのか。人と唄が共に響きあう時代がかつてあったのだ。全盛期の小梅を知る人は高齢の方が多いので、映画の宣伝方法が難しいと、この映画の制作者・増永研一は語る。入りを心配していたのだが延長上映が決定した。ホッ。
一二月六日(土)?一二月一二日(金)まで、東京・JR東中野駅から徒歩一分の「ポレポレ東中野」で一〇時四〇分から上映。お見逃しなく。(本田政昭)
▼田母神俊雄前空幕長の論文が大変な問題となりましたが、歴史認識に誤りがあると指摘されています。全文を読みましたが、ずいぶんと手前勝手な論理もあるものだと驚きました。
学校の歴史の授業では、日本の歴史は近代や現代まで教える授業時間が足りない、とよく言われています。そのため、近代史や現代史について子どもたちは知らないのではないかと指摘されます。いっそのこと、現代から近代、近世へと遡って学ぶほうが興味が持てると思います。
小学六年の息子は、自分の興味のある第二次世界大戦から日本の歴史について本を読み始めました。先日、「二・二六」と「五・一五」は、どちらが先なのか、自衛隊のいちばん上の人は誰かと訊かれました。幼い頃から、憲法や戦争について、また、東京大空襲で親戚が犠牲になったことなど、折に触れて親子で話をしてきました。そろそろ独立して、自分でリテラシー能力を発揮し、知識を獲得する時期が来たのだと思います。(樋口惠)