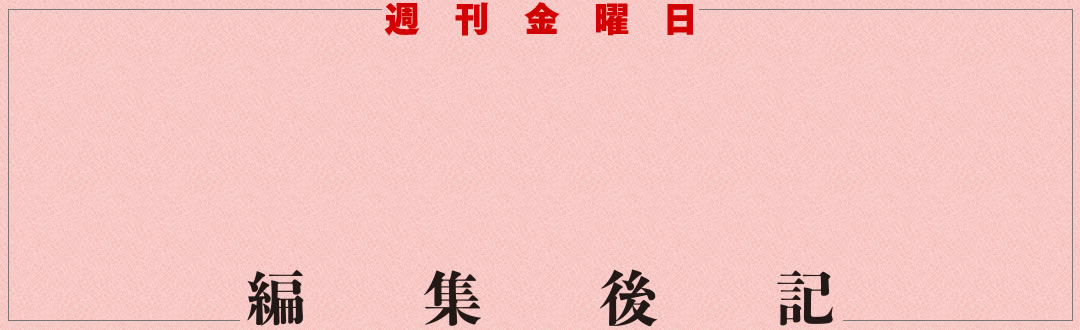729号
2008年11月28日
▼「世界の当事者になる」。雨宮処凛さんが『ビッグイシュー』誌で連載しているコラムのタイトルだ。
その核心は、この時代・この社会に対して「問題」を提起する主体性である。他人から提供された選択肢を鵜呑みにするのではなく、どれだけの選択肢が現実に存在しているのか確認し、そこで不服ならば新しい選択肢そのものを自ら創り出していくという生き方。
誰もがはじめから当事者であるわけではない。しかし誰でも当事者になることはできる。故・久野収編集委員は、職業倫理に基づく当事者性を「市民」と定義した。
選ぶべき選択肢を他人から操作され、無知の状態に追いやられたままそれに気づかず、いつわりの自由にうかれる「幸福な奴隷」という生き方もある。
もちろんその選択肢を否定はしない。しかし少なくとも私はそれを拒否したい。世界を、歴史を、自分自身をみずからの手に取り戻すために。(高橋望)
▼本誌が印刷、製本、発送されるまでを受け持つ工場の「見学会」を社内研修として行なった。
校了(下版)してから購読者の郵便受け、または、書店の店頭に置かれるまでの工程は驚くほど複雑だ。そのうえ、常にそのパートごとのタイムリミットが決められている。
千代田区内でデータ化された『週刊金曜日』は杉並でページ組され、真夜中に都外に運ばれる。ここで会社も組織もまた別になり、前身が日産ディーゼルの組み立て工場だったという、巨大な印刷・製本ラインにまわされる。
オフセット輪転機がうなりを上げ夜明けまでに印刷。無人運搬機がピーコピーコと言いながら縦横に動く。朝、「深夜勤」から「日勤」組に引き継いでの製本。スタッフの雇用形態の違いが制服や腕章によって別けられている。
これでもやっと「工程」の半分くらいだろうか。一度、下版からポストまでの密着ルポというのをやってみたい。(土井伸一郎)
▼戦後史の戦争と平和をめぐる長い攻防で二〇〇八年が特筆すべき年として後世に記憶されるようになると思われるのは、言うまでもなく二月の名古屋高裁イラク空自派遣違憲訴訟判決に依る。判決は米軍の軍事輸送に加担している事実から現代の戦争概念に照らせば事実上日本は戦争状態にあると見なし、それゆえ私たちの「平和的生存権」が犯されていると認定している。同時にそれは、「戦争ができる国家にするために改憲が図られている」といった類の認識の根本的再考を促していたはずだ。すでにこの国は戦争をし、子どもたちを始め人々の命を奪う行為に手を染めている以上、「戦争ができる国家」になりかねないことが焦眉の急であるかのような言説は錯誤でしかない。今回の大統領選で米国が戦争を止める意志は毛頭ない現実を改めて知らされたはずだが、今問われるのは日本自身の戦争を即刻中止させる決意と努力である。それを抜きに、いくら「九条」を云々しても空しい。(成澤宗男)
▼発売日の一週間前に訃報を聞く、という悲しい事態が起きてしまった。今週号の対談で辛淑玉さんと語っていただいた山田泉さんが二一日、がんのために亡くなられた。掲載誌を持ってお見舞いに行こうと思っていたのに、それもかなわなくなった。対談をまとめたゲラ刷りをお送りし、読んでいただけたこと、返信の最後に「辛さんとの対談ギリギリ実現セーフ!! ありがとう」と書かれていたのがせめてものなぐさめである。
「いのちの授業」で知られる山田さんに、あえてその話ではなく性教育や学生時代のことなどを話していただき、別の一面を知ることができた。病を押して対談をしてくださったことに心から感謝している。さようならは言いたくない。彼女はこれからも多くの人の心の中で生き続けるだろうから。
在りし日の山田さんをご覧になりたい方は、ドキュメンタリー映画『ご縁玉』をどうぞ。上映の問合せはパンドラ(電話番号 03・3555・3987)まで。(宮本有紀)