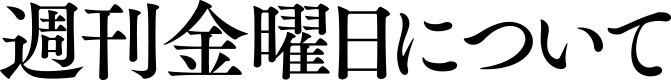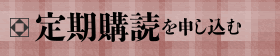「意外と面白いぞ」、金曜日
編集長挨拶
週刊金曜日 編集長 文聖姫

みなさま
新編集長の文聖姫です。
私は在日コリアンです。1世の父、2世の母のもと、日本で生まれ育ちました。小学校から高校までは朝鮮学校に通い、青山学院大学を卒業した後、『朝鮮新報』で20年間、記者をしていました。いわば人生の多くを在日コミュニティー社会で過ごしてきたわけです。拉致問題をきっかけに朝鮮新報社を退職した後は、東京大学大学院で北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の経済を研究し、博士の学位を取得しました。研究活動をしている最中、縁あって『週刊金曜日』で働かせていただくことになりました。2017年からアルバイトを始め、翌18年に社員公募に応募し、同年5月に社員として採用されました。19年6月からは小林和子前編集長のもと、副編集長を務めてまいりました。
そんな私も、『週刊金曜日』の存在にはおおいに勇気づけられてきました。それは、小さな声、名もなき人々の声をすくいあげ、それをきちんと活字にして伝えてくれている数少ない媒体だと思うからです。あらゆる人々の人権を守り、平和を守り、さまざまな差別に反対し、言論の自由を守る存在が『週刊金曜日』だと思っています。
既存のメディアに物足りなさを感じていた人たちが『週刊金曜日』を作り、みなさんにお届けするようになってから、早28年。再来年の2023年には創刊30周年を迎えます。大手出版社の週刊誌のように大々的な広告も展開できませんが、定期購読者をはじめとする多くの方々に支えていただき、ここまで続けることができました。
しかし、私たちを取り巻く環境は決して楽観的なものではありません。新型コロナはまだまだ収まる気配は見えません。富の分配と言いながら、格差はますます広がっています。いまこそ『週刊金曜日』が力を発揮する時だと思います。こんな時だからこそ、どんな社会を作っていけばいいのか、そのような点でヒントを与えられるような、未来に希望が持てるような雑誌を作っていきたいと思っております。
2021年11月
文聖姫(ムン ソンヒ)
発行人挨拶
週刊金曜日 発行人 植村隆

みなさま、こんにちは。『週刊金曜日』社長兼発行人の植村隆(うえむら・たかし)です。コロナ禍で、日韓の往来が難しくなったため、2020年12月で、韓国のカトリック大学招聘教授を辞め、本誌の経営に専念しております。依然として本誌の経営難には変わりはありませんが、社内改革や経費削減などの努力を続けており、少しずつ改善されてきました。
このほど、第9代編集長に在日韓国人の文聖姫(ムン・ソンヒ)が就任しました。本誌史上初の選挙による、編集長就任です。前任の小林和子に続いて、本誌編集長は2代続けて女性となりました。日本の言論機関で、選挙で編集長を選んだという話はあまり聞いたことがありません。ましてマイノリティの女性が編集責任者になるのも稀有だと思います。「開かれた」本誌ならではの選抜システムだと思います。新編集長の下で、誌面も、さらに読みやすく充実したものになると信じております。
『週刊金曜日』は1993年の創刊以来、人権や平和、言論の自由を守るために、果敢にペンを執ってきました。私は2018年9月、前任者の故北村肇さんから、本誌の責任者を引き継ぎました。「リベラルなジャーナリズムの灯火を消してはならない」という思いで、経営再建に取り組んでおります。みなさま、『週刊金曜日』を応援してください。どうぞよろしくお願いします。
定期購読に支えられる雑誌
定期購読中心の3つの理由
『週刊金曜日』は、広告に依存せず定期購読者に支えられることで、「真実」を報道しています。
一般的にテレビ、新聞、雑誌は企業などスポンサーからの広告出稿がなければ成り立ちません。そのため、大切な情報や意見でもスポンサーや権力に配慮して大手メディアが伝えないことがあります。
そこで『週刊金曜日』は定期購読料を払ってくれる読者に、主たるスポンサーになってもらい、発刊しました。そのため広告主である企業に遠慮することはなく、政官権力の圧力も『週刊金曜日』には効きません。
儲けよりも大事なことを伝えられる雑誌作りを続けています。
定期購読料が前払いされているため、毎号の売れ行きに左右される心配がありません。そのため世間の好奇心を満たすために迎合する編集方針ではなく、少数者の視点にも立ちながら、伝えなければいけないことをじっくり考えることができる編集方針をとっています。
書店がない地域にも毎週届けることができます。また、北海道から沖縄まで送料均一にしておりますので、全国、同じ値段でお読みいただくことができます。
創刊の想い
誌名の由来
反ファシズムのフランス人民戦線が刊行した『Vendredi(ヴァンドルディ=金曜日)』。 それに刺激され、治安維持法制下の京都で発刊されるも弾圧により途絶した『土曜日』。 戦後日本の民主主義を支え、34年を積み重ねたが部数の低迷により廃刊した『朝日ジャーナル』。 それらの志を継承し、さらに発展させるものとして、哲学者・久野収が『週刊金曜日』と命名。

創刊のことば
歴史学者J・E・アクトンの有名なことば「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」に象徴されますように、権力の腐敗がほとんど法則的であることを前提として、近代の国家は腐敗を構造的に防ぐ手段たる「三権分立」を創出しました。しかしこの三権はいずれも国家権力に属するために、しばしば癒着あるいは独裁化に陥りやすい現象がみられます。
この「癒着あるいは独裁化」を監視して未然に防ぐための最も有効な働きを示してきたのがジャーナリズムです。腐敗しつつある権力は、国民に「知られる」ことをまず最もおそれます。知られなければ国民の怒りも起きようがないはずなのですから。したがってジャーナリズムは、国家権力としての「三権」からは全く独立した市民のものでなければならず、そこに俗称「第四権力」たる意味も役割もあるわけです。民主主義社会にとって健全なジャーナリズムが必須条件でもあるゆえんでしょう。
しかしながら、そのような第四権力としてのジャーナリズムも、国民の間に信頼がなければ影響力はありません。一般的に週刊誌の信頼度が過去に高くなかったのは、センセーショナリズムや羊頭狗肉・エログロ・プライバシー暴露に走りすぎ、正確性や取材倫理・批判精神・報道対象などの点で真のジャーナリズムからかけ離れていたからでしょう。
ジャーナリズムが国民の信頼を失うもう一つの大きな原因に、国家権力との癒着あるいは国家権力の広報機関化があります。三権を監視する役割のはずが、三権の補完物と化しているのでは、第四権力としての存在理由もなくなってしまいます。
日本敗戦からまもなく50年。日本列島はゴルフ場などで環境破壊がすすみ、去年は日本軍(自衛隊)の海外派兵が強行され、金権政治の腐敗構造も極点に達していることが国民の前に明らかになりました。この重大な時期に、日本のジャーナリズムははたして第四権力の名に恥じぬ役割をつとめているのでしょうか。
『月刊金曜日』1993.7.23
久野 収 「発刊に寄せて」

支配政党の金権腐敗、この政党に巨額献金する経済主流が見逃す無責任なマネーゲーム、巨大化したマス文化の画一化作用、これらは相乗効果を発揮して、いまや底無しの様相を呈し、民主主義の市民と世論を呑み込む勢いである。
この三つの荒廃には、さまざまな超越的、イデオロギー的批判が下されている。しかし、あまりものをいうようにも見えない。
むしろ、いま必要なのは、前途をどうすれば明るくできるか、その勢力と方法の芽生えはどこにあるのかをはっきりさせる内在的、打開的批判であり、この批判を職業とし、生活し、思想する主権市民の立場から実物教示してみせる仕事である。
われわれは、34年を積み重ねた『朝日ジャーナル』の一貫した志の中断をはなはだ残念に感じ、ここにその志を継承し、さらに発展させる週刊誌を新しく発刊しようとする。
いかなる機構、どんな既成組織からも独立し、読者と筆者と編集者の積極的協力の道を開き、共同参加、共同編集によって、週刊誌における市民主権の実をあげるモデルの一つを作りたいと願っている。
われわれをバックアップしてくれるのは、34年に及んだ『朝日ジャーナル』だけではない。1935年、ファシズムの戦争挑発を防ぎ、新しい時代と世界をもたらすために、レ・ゼクリバン(作家・評論家)が創刊し、管理する雑誌として出され部数十万を数えた『金曜日(ヴァンドルディ)』の伝統もある。「自由な作家・評論家と自由な市民から成る読者大衆との直接交流」の熱望を生かすために、ロマン・ロラン、アンドレ・ジッド、哲学者アラン、マリタン、バンダ、物理学者ジョリオ・キュリー夫妻以下四十数名の編集者の名前を表紙にずらりと刷り込み、社説、発言、政治ニュース批判、社会時評、海外情報、芸術、科学、哲学、大衆娯楽の各欄を大きく取り、長編連載小説まで組み込んだのが、この週刊誌であった。さらに『金曜日』に刺激され、1936年、京都で発刊され、京阪神だけで一万部近くに達し、「生活への勇気、精神の明晰、隔てなき友愛」をモットーにした週刊誌『土曜日』の伝統も加わっている。
読者諸君、執筆者諸君の積極的参加を心から期待したい。
1992年10月30日