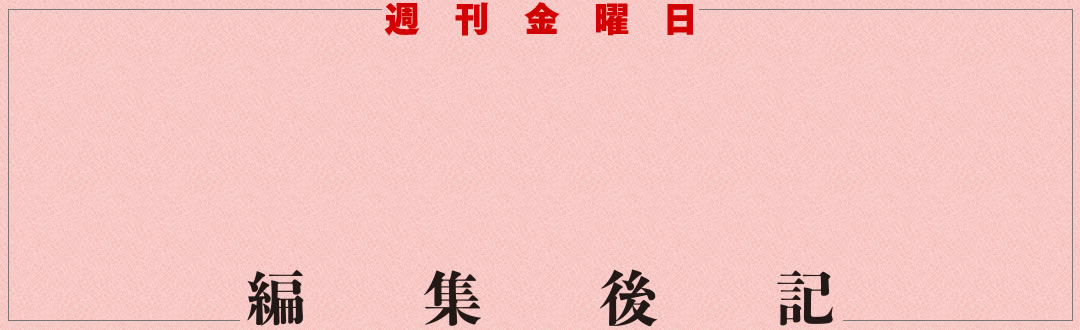1473号
2024年05月24日
▼夜、スマホをみると、高齢者施設にいる92歳の母から何件もの着信履歴。ドキッとして折り返し電話をすると、「NHKで怖い病気が流行っているっていうから、気をつけろしよ」。きっと?人食いバクテリア?=劇症型溶血性レンサ球菌感染症のことだろう。
昔からテレビや新聞で危険情報に触れると、離れて暮らす娘たちのことが心配になるらしい。危険察知度が高く生真面目な母。「いつもありがとね」。毒タコだの黄砂の降下だの、母からの危険情報はいろいろあるけれど、PFASについてはない。私の不安材料はずーっとこれ。沖縄にいる家族のことが特に心配なんだ。
この2月、ダムの貯水率が低下して、(汚染が問題になった)嘉手納井戸群からの取水を一時再開したと聞いたときには絶句した。もちろん暫定値をクリアするよう浄水処理はなされるわけだけど。
今週号で同僚がPFAS特集を組んでくれた。後手後手の対策をなんとかしたい。(小林和子)
▼今週号で映画『生きて、生きて、生きろ。』の島田陽磨監督にインタビューした。福島「復興」の陰に隠れた被災者の心の問題に焦点を当てた作品だ。東日本大震災と原発事故の後、アルコール依存症や悪夢など心の病を患う人たちが登場する。島田監督は「当事者の問題として切り捨て矮小化してはならない」と言う。「同じ状況に置かれたら、自分を含め誰しもがなり得る」。社会共通の課題だとわかるよう、島田監督は映画の中で、米国の核軍拡路線や日本の原発導入の経緯から説き起こす。
映画の舞台は福島と沖縄。いずれの地域でも戦時、戦後の歴史が住民の心に暗い影を落としていることが作品を通してわかる。島田監督は「メンタルヘルスは一番大事な生活の基盤であるにもかかわらず、目に見えず、報道もされにくい」という。若年層のホームレスや医療過疎地で苦しむ人々など「日の当たらない場所」にカメラを向けてきた島田監督らしい、示唆に富む作品だ。(平畑玄洋)
▼5月10日号の「風速計」(崔善愛編集委員)で取り上げた金成日さんから、指紋押捺拒否による罰金3万円に対し、抗議の意思表示で支払わなかったのは「1万円」ではなく、日本による韓国併合が行なわれた年をとって「1910円(年)」の間違いだと連絡をいただいた。金さんにはお詫びするとともに誌面にご登場をお願いし、読者にはあらためて「その後」などを含めて紹介したいと思う。
もう一件はイベントを宣伝したい。東京・町田にある西東京朝鮮第二幼初中級学校を知ってもらおうと同学校で、6月8日(土)18時から映画『アイたちの学校』(高賛侑監督)の上映会を行なう。500円(高校生まで無料)でキムチの試食付き。キムチを食べて学校を支援する取り組みもあり、今月はセロリと白菜のキムチをおいしくいただいた。問い合わせは、朝鮮学校を支える町田市民の会(090・3692・9382瀬戸)。
(吉田亮子)
▼「うそだろ」。ドラマ「大病院占拠」と「新空港占拠」で思いもよらぬ事態に遭遇した時、主演の櫻井翔が発する言葉だ。
5月6日東京ドームで開催されたボクシング、井上尚弥対ルイス・ネリの4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチは劇的な試合展開となった。無敗の絶対王者井上が1回にダウンを喫してしまう「うそだろ」。だが、プロ初のダウンでもあわてることなく、あえて8カウントまで立たなかった。その後ダウンを奪い返すと6回TKOで勝利した。勝敗の分岐点はこの「井上の8秒」だった。
なお、この日は他にも世界戦があり、バンタム級4団体の世界王者がすべて日本人選手となった。ただし、元々は井上選手が獲得して返上したベルトである。「黄金のバンタム」と言われるボクシングのバンタム級。まさに「黄金週間」を締めくくる一日となった。5月6日はボクシングの日として語り継がれるだろう。(原口広矢)