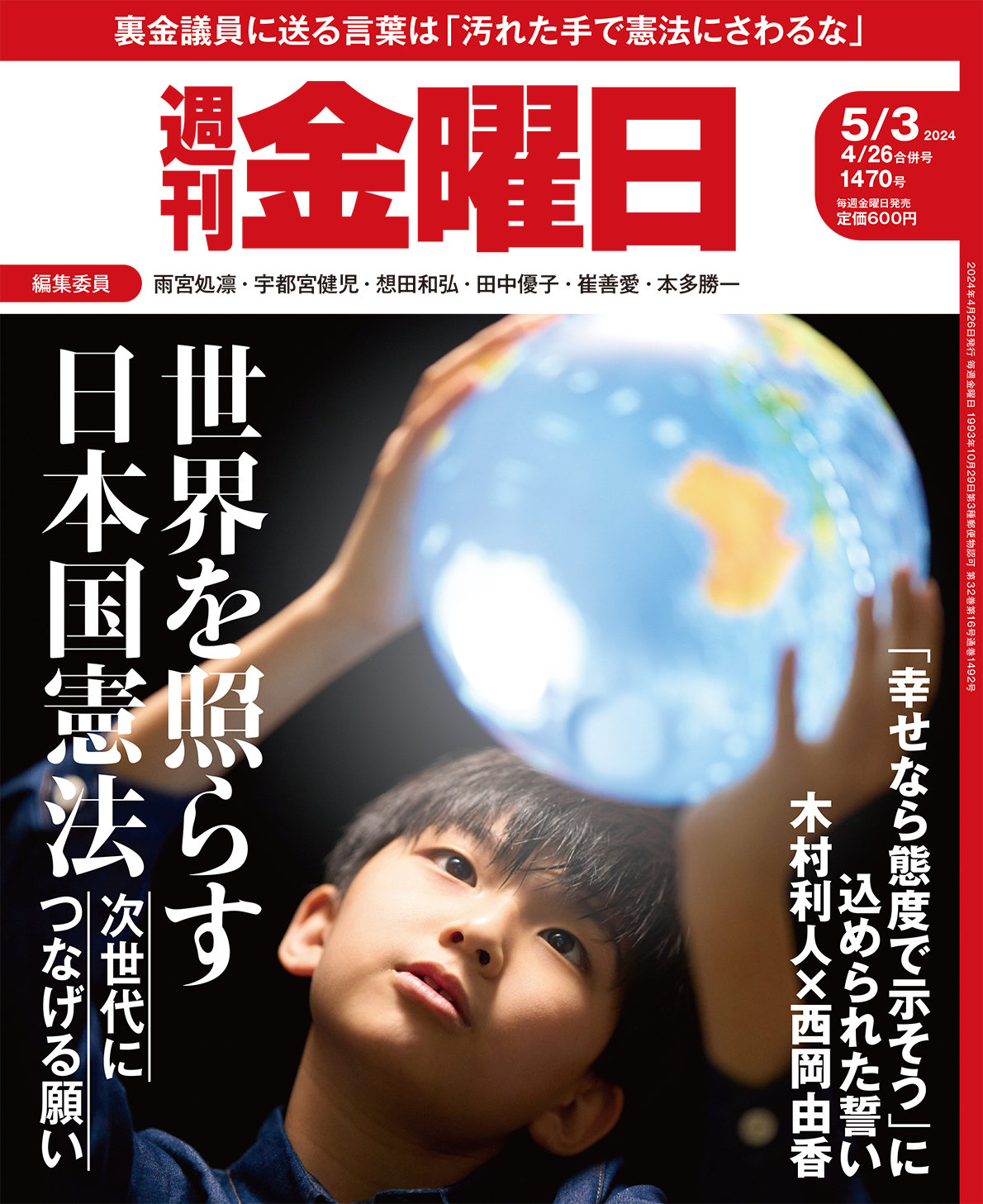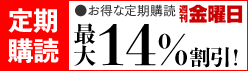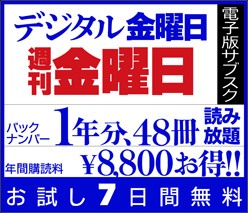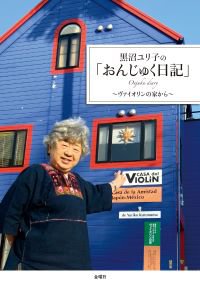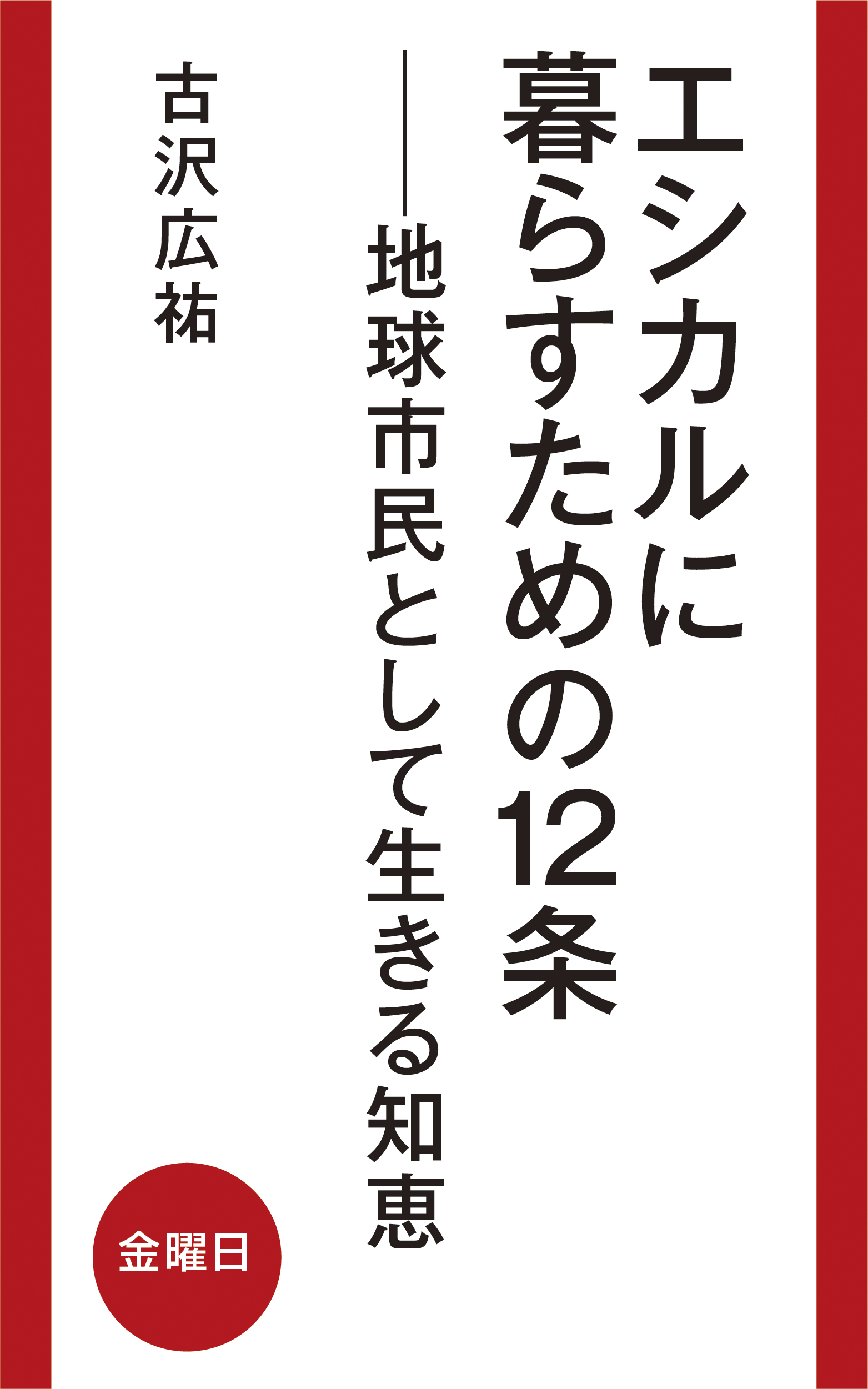【タグ】マネタリーベース|日本銀行|消費者物価指数|異次元の金融緩和|黒田東彦
日銀は「金融緩和中毒」なのか
高橋伸彰|2021年5月5日12:23PM
今回の点検でも、「日本の適合的な期待形成のメカニズムは、より複雑で、粘着性が高い」と繰り返したうえで、目標実現を阻む新たな要因として「弾力的な労働供給が賃金上昇圧力を吸収してきたこと、また、企業の労働生産性向上がコスト上昇圧力を吸収してきたことも影響している」と述べる。
相対的に低い賃金でも就業を望む女性や高齢者の積極的な労働参加が、全体的な賃金上昇を抑えたり、また、小売業におけるレジの無人化など人手不足に対応した企業による省力化・効率化投資が、コストの上昇圧力を吸収したりしていることが結果として、物価上昇を抑制していると言うのだ。
日銀は今回の点検後も、2%の物価安定目標を実現するために「持続的な形で、金融緩和を継続していく」と主張するが、当初2年で達成する予定の目標を8年経ても実現できない金融緩和の点検にとって必要なのは、単に効果があったか否かではなく、緩和の長期化に伴うコストやリスクを考慮しても、なお「国民経済の健全な発展に資する」政策か否かの検証である。