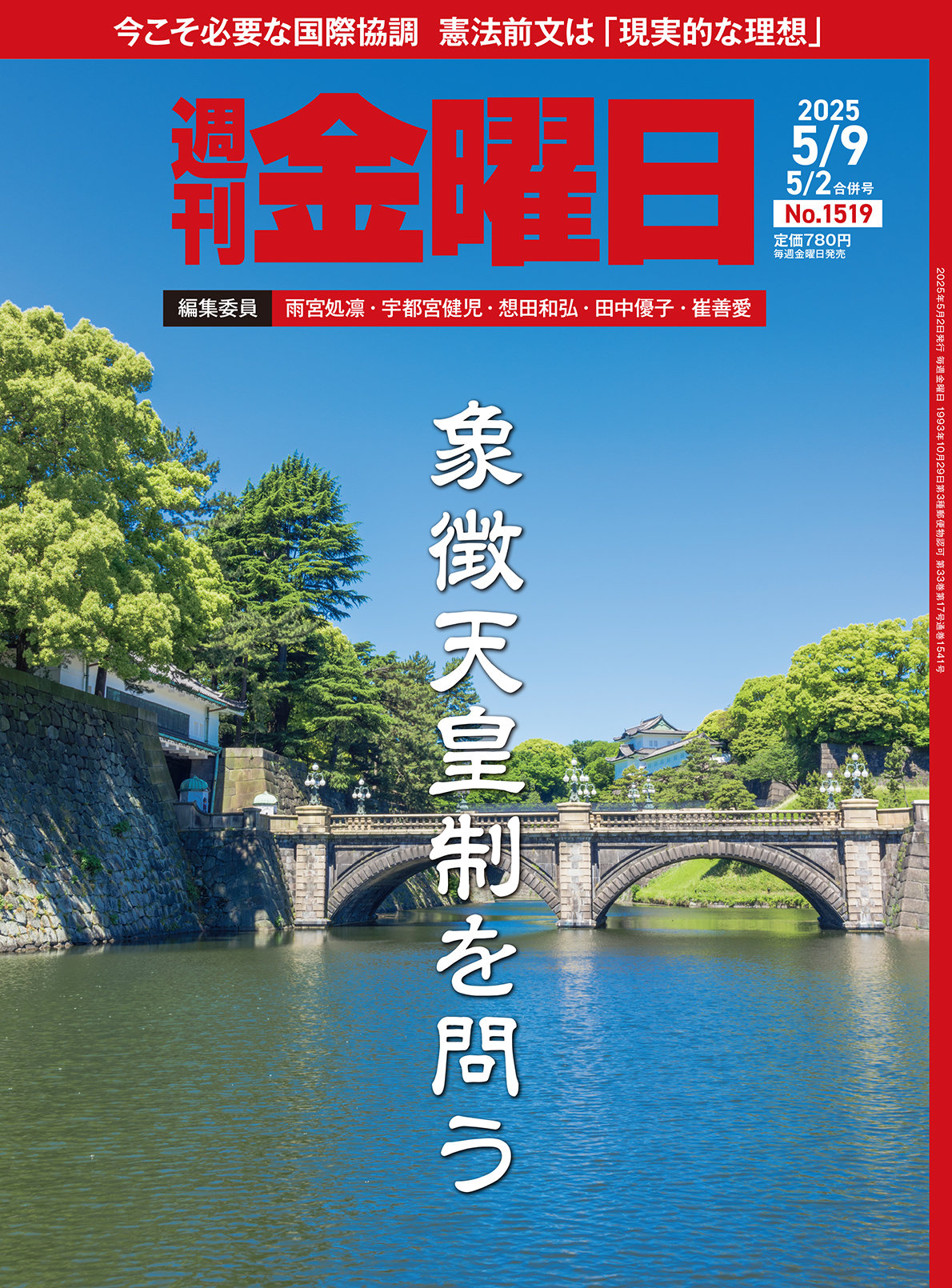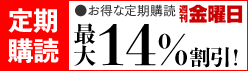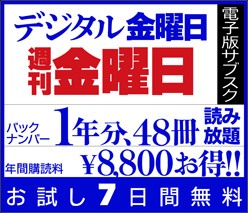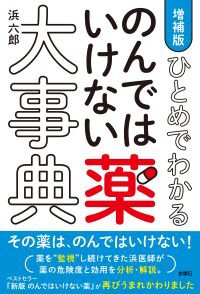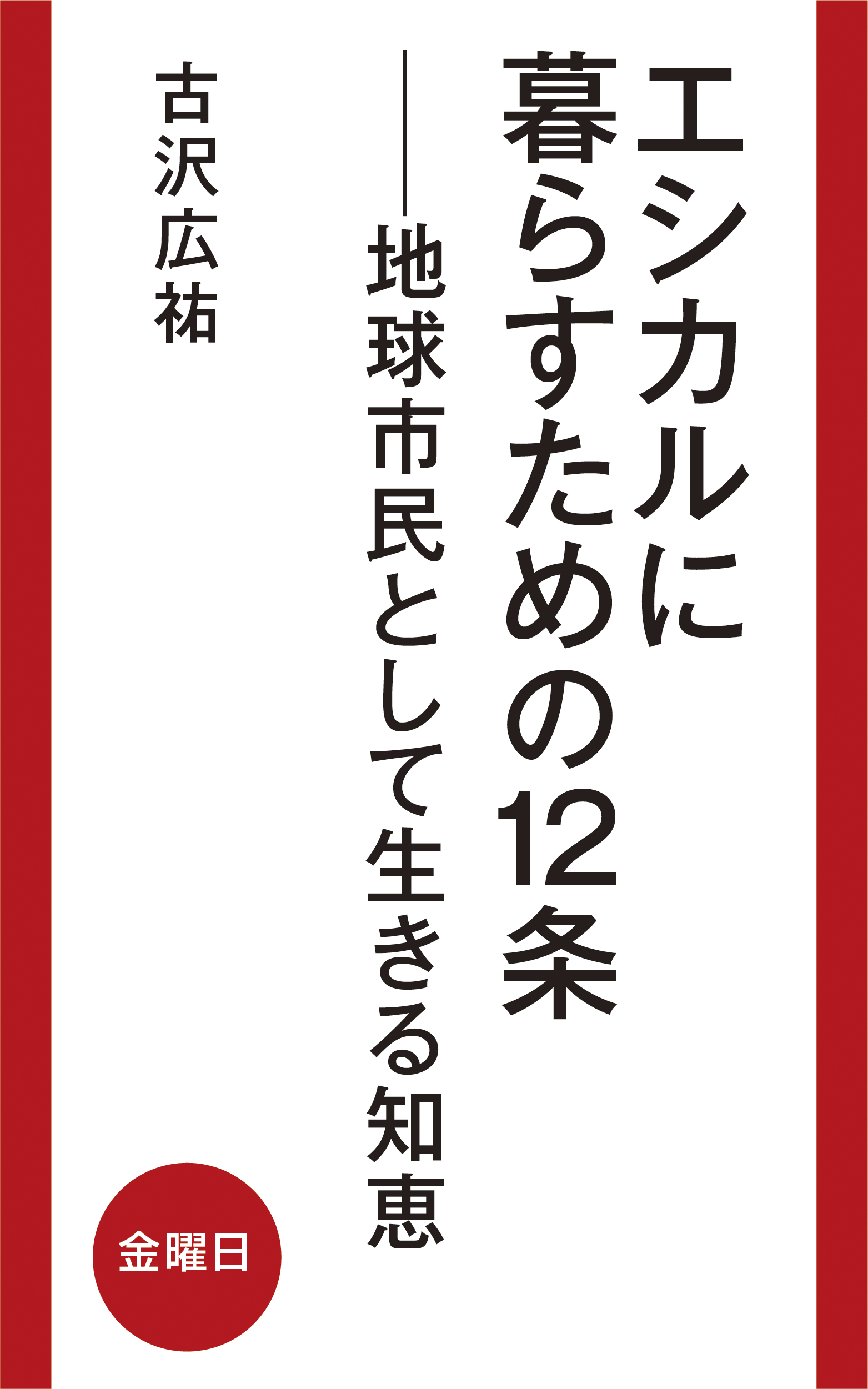【タグ】ジェンダー|ジェンダー平等|ハラスメント|フェミニスト|票ハラ
議員のいじめ、有権者の「票ハラ」 女性の政治参画阻むハラスメント対策急務
古川晶子・ライター|2025年5月2日7:10PM
女性の政治参画は、多様な人々の声を政策決定の場に届ける第一歩だが、それを阻む要因の一つに、議員活動や選挙活動中のハラスメントがある。NPO法人女性人権機構が3月26日に開催したオンラインシンポジウム「ハラスメントのない議会に」では、女性の政治参画を阻むハラスメントの実態が複数報告された。

2021年に改正した「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(候補者男女均等法)」では、候補者や議員の男女格差をなくすために国および地方公共団体が施策を策定・実施する責務を有することや、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントの防止や対応をすることが定められている。
労働政策研究・研修機構の内藤忍さんによれば、同法に基づき各自治体でハラスメントを防止する条例が制定されているが、その多くが議員同士、あるいは議員から自治体職員へのハラスメントを想定しているという。しかし、全国フェミニスト議員連盟が21年に実施した議会内での少数派(特に女性)に対する「いじめ」の実態調査では、「ハラスメントを受けたことがある」という回答のうち、「同僚議員から」が81・0%、「有権者から」が76・2%だ。内藤さんは「女性は議員からだけでなく有権者・支援者からのハラスメントを受けている」と指摘し、こうした事態に対応する相談体制や救済制度が必要だと述べた。
第三者の介入が重要
女性議員・候補者のサポート団体Stand by Women代表の濵田真里さんは、有権者・支援者からのハラスメントとして、街頭演説中の接近、不審な電話やストーカー行為、選挙の手伝いを条件に交際を求める、デマや誹謗中傷を拡散するなどの例を挙げ、「こういった行動を取る人たちは票を持っていることを振りかざしている」と批判。支援をやめることや誹謗中傷などをほのめかして相手を従わせようとする嫌がらせは「票ハラ」と呼ばれ、女性がターゲットにされることが多い。
濵田さんは議員へのハラスメントをなくしていくために、議員一人に問題を抱え込ませない仕組み作りと、ハラスメントを受けたときに間に入って被害を抑える第三者介入が非常に重要だと語った。
愛媛県南宇和郡愛南町議会の金繁典子議員は、高齢男性が圧倒的多数を占める議会では「多様な考えが議会に反映されにくい」と指摘する。24年9月、「えひめ女性議員ネットワーク」を発足し、同時に行なった県内女性議員25人へのアンケートを紹介。中には「全職員の指揮を低下させたと『推察される』」などという不合理な内容の問責決議をされるなど「一般常識が関係ないところで決定される」嫌がらせの例も。金繁さんは「町村議会議長会で相談機関を設置し、判定や助言をしてほしい」と訴えた。
24年10月、国連女性差別撤廃委員会は、ジェンダーに基づく暴力から女性の議員を守るための、政府や議会から独立した救済機関をつくるよう日本政府に勧告している。各政党の相談窓口などもあるが、第三者機関であることが望ましい。Stand by Womenが23年に開設した議員向けハラスメント相談窓口は、無所属議員や候補者も利用できる。国際社会から周回遅れのジェンダー平等を少しでも底上げするため、このような第三者機関の設置、相談・救済制度の整備が急務である。
女性人権機構副理事長の林陽子弁護士は、「日本での議員に対するハラスメント法制をどうしていくかを考える時期に来ている」として、今後、政府等に具体的に働きかける意向を示した。
(『週刊金曜日』2025年4月4日号)