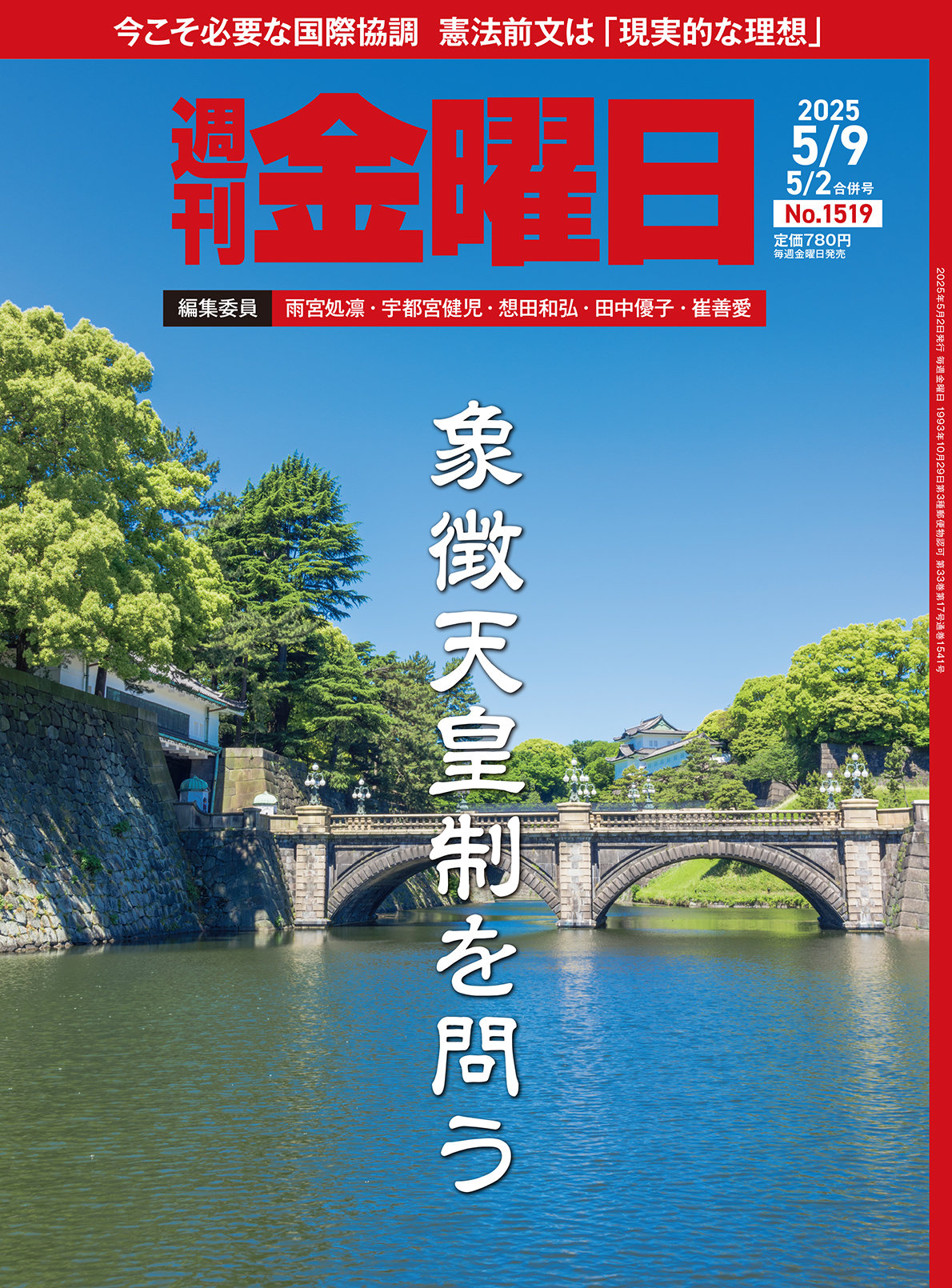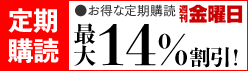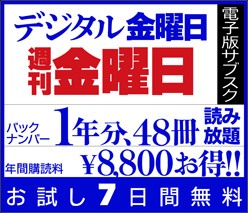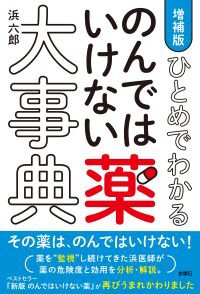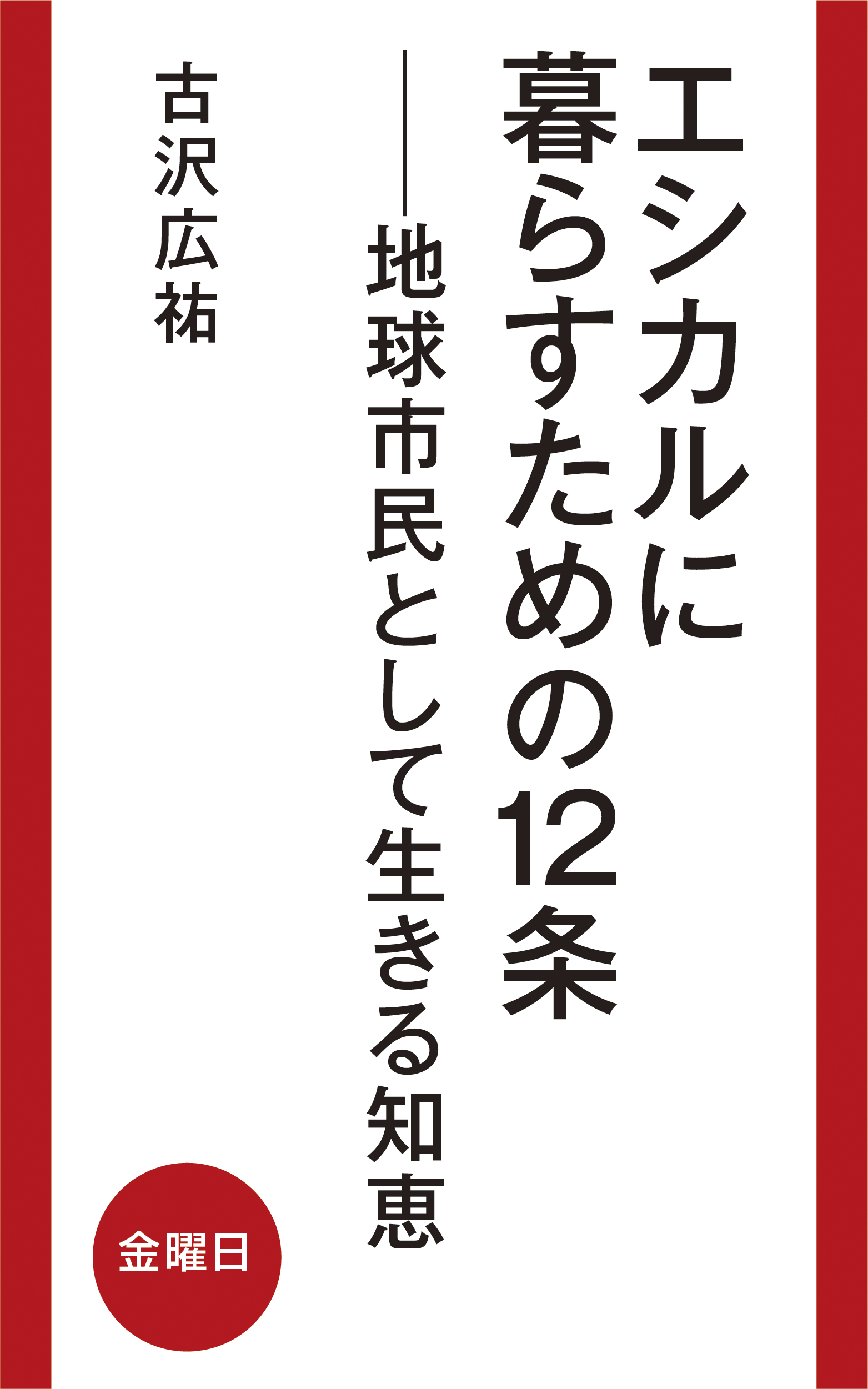狭山事件・冤罪被害者の石川一雄さん死去 差別に苦しむ人々結んだ闘い
みなみあめん坊・作家|2025年5月2日5:27PM
冤罪被害者の石川一雄さんが3月11日夜、故郷である埼玉県狭山市の入間川病院で死去、86歳だった。昨年11月1日に東京・日比谷野外音楽堂での市民集会で挨拶した石川さんは「狭山から日比谷まで3回も転げた」と語っていた。その目は腫れ、ほとんど視力を失っているようにも見えた。

昨年末から石川さんは肺炎で妻早智子さんの地元、徳島市の病院に入院。年明けに「どうしても狭山に帰りたい」と車で故郷に戻ったが回復には至らず、誤嚥性肺炎で生命を閉じた。石川さんの死を知った冤罪・大崎事件の鴨志田祐美弁護士は「再審法の不備で救済が遅れ、存命中に再審無罪を勝ち取れず、この世を去る犠牲者が出てしまった。なんとしても今国会で再審法改正を実現させることを石川さんの御霊に誓う」ことをインターネットに記した。
袴田事件の袴田巖さん(89歳)は冤罪を晴らしたが、検察の異議申し立ての抗告で歳月がかかり、死刑執行の恐怖から今も拘禁症に苦しむ。再審法改正を求める幅広い世論の高まりに議員連盟が結成され、与野党の国会議員377人が参加。全国の地方議会で524の意見書採択。今国会では成立が見込まれているが、石川さんには間に合わなかった。
「石川青年」は、社会の底辺で差別に苦しむ多くの人々を結び付ける闘いの象徴になっていた。狭山事件再審弁護団の団長、中山武敏弁護士(81歳)もその一人。石川さん同様に、自らも福岡県直方市の被差別部落に生まれた中山さんの母は、廃品回収のリヤカーを引きながら育ててくれた。家族のために中卒で働きに出た中山さんにとって、警察・検察の脅しや誘導に屈し、書けない文字で「脅迫状を書いた」と自白した石川青年の心中は痛いほどわかった。
中央大学の夜間で働きながら司法試験に合格した中山さんは、1963年の高校女子生徒殺人事件=狭山事件=の見込み捜査で被告人に仕立てあげられた石川さんの弁護団に2審から加わる。さらに軍人遺族に厚く民間戦災者に薄い、この国の戦後補償の冷酷を告発した東京大空襲訴訟の弁護団長としても奔走。この人柄に東京都知事選挙に立った宇都宮健児弁護士(元日本弁護士連合会会長)や、自民党の顧問でもあった小林節弁護士も狭山弁護団に参加した。
無学につけ入る捏造捜査
狭山事件と袴田事件に共通するのは証拠捏造による自白誘導だ。袴田事件では犯人が味噌樽に入れたとされる「血染めの衣類」を、検察側が証拠開示して袴田さんの無実が明らかとなった。狭山事件でも石川さんの自宅鴨居で〝発見〟された「脅迫状を書いた」という万年筆のインクが、被害者が使っていたものとは違っていたことが証拠開示で判明した。
石川さんは94年12月21日に千葉刑務所から仮出獄。不当逮捕から31年7カ月。刑務所から自宅までの車中から見た自動販売機が何の機械かわからなかった。「冤罪の受刑生活を解かれども故郷に立ちて吾は浦島」と詠んだ。家庭は貧しく学校に通えず満足に読み書きができなかったが、獄中で広辞苑を差し入れてもらい自学自習で文字を覚え、短歌も詠めるようになった。文字を奪い返すのは自らの生命を賭けた闘いだったのだ。
31年にわたる獄中生活は韓国軍事独裁政権下の政治犯・徐勝氏、南アフリカ共和国のマンデラ元大統領の獄中生活より長い。
大阪府池田市の被差別部落で生まれ育った筆者は16歳の高校生の時、東京高裁公判を傍聴。法廷で懸命にメモを取って弁護団に手渡す石川さんの姿は忘れない。公判後は日比谷公園の一角で数十人ずつ集まった。公判を重ねていく度に数百人、数千人へと増えて最後には公園を覆い尽くす数万人の人々が集まった。しかし2審判決は、1審死刑を取り消す無期懲役。最高裁は77年にこれを確定。東京拘置所から千葉刑務所に移されてからも、僕は千葉に通った。石川さんも取り戻した文字を駆使し、獄中から全国の支援者に手紙を書き続けた。
(『週刊金曜日』2025年3月21日号)