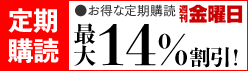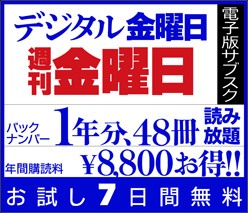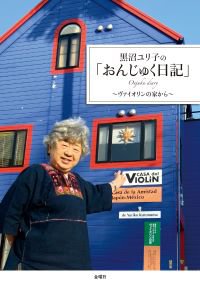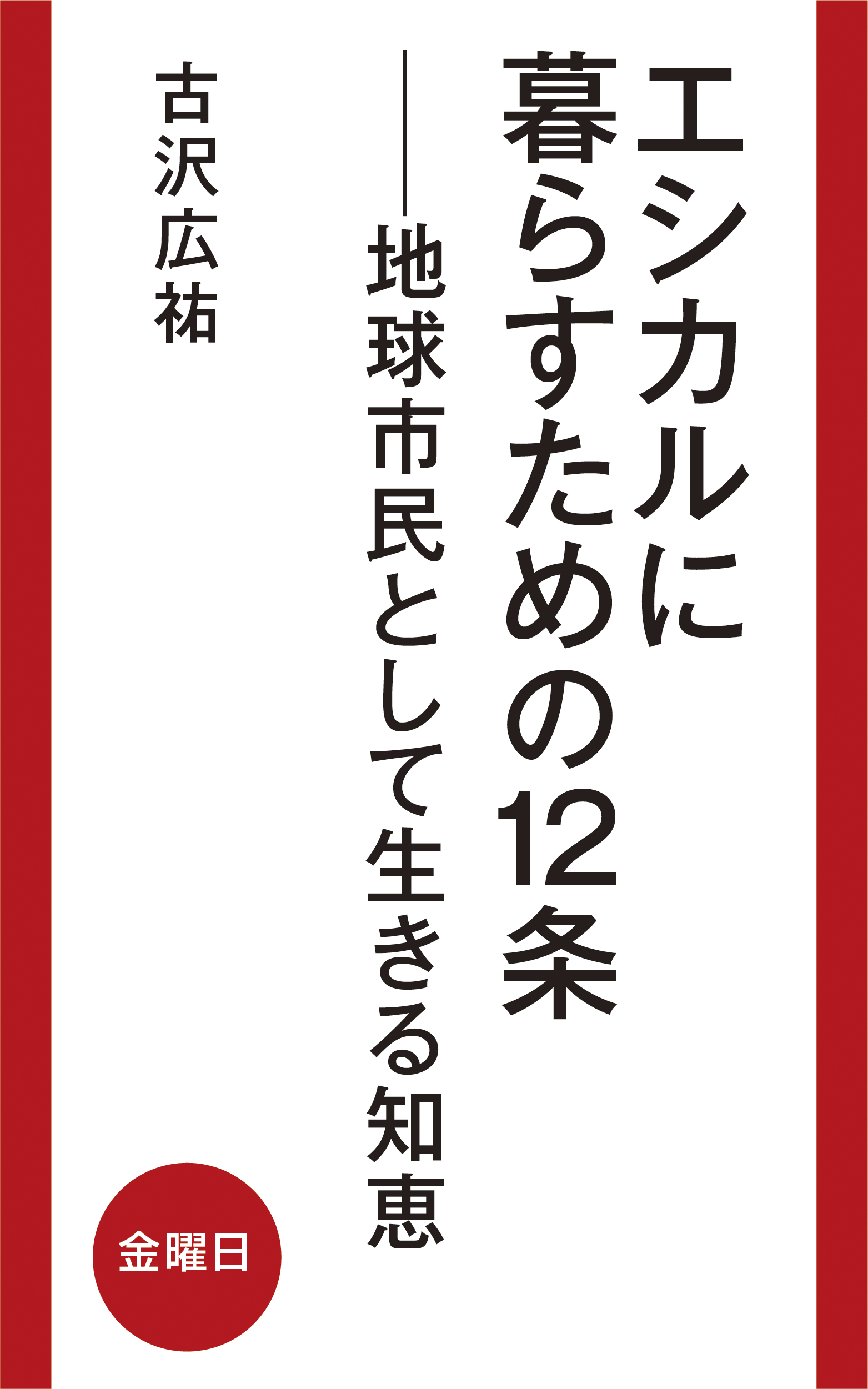【タグ】キャラメルボックス|サンシャイン劇場|サンタクロースが歌ってくれた|成井豊|演劇|阪清和
キャラメルボックス復活公演
劇団を率いる成井豊の思いとは
2021年12月2日6:36PM

活発な公演活動で人気があった2019年5月に突然「活動休止」を発表し、翌日には劇団を支える制作会社の倒産が報じられるなどファンを驚かせた「演劇集団キャラメルボックス」。休止から2年半あまり、今年12月に復活公演『サンタクロースが歌ってくれた』の上演にこぎつけた人気劇団にいったい何があったのか。約2年間の苦闘と原点回帰への思い、俳優としての自立も迫られた劇団員らの復活公演にかける熱い感情も含めて、劇団を率いる座付き作家で演出家の成井豊が休止後初めてメディアの取材に口を開いた。
『サンタクロースが歌ってくれた』は人気演目で、成井が28歳の時に書いた作品。大正時代が舞台の探偵映画の主人公たちが、逃げた犯人の行方を追って銀幕から飛び出し、映画を見に来た現代の20代の女性たちと奮闘する物語だ。
1989年に初演し、92年、97年、2010年に再演。今回が劇団最多の5回目の上演となる。
「自他ともに認める代表作だから」と復活公演に選んだ理由を語る成井。「やっぱり節目には一番大事な作品をみんなでやろう」と呼び掛けたのだという。
頼まれて探偵のまねごとをしていた芥川龍之介が、手伝ってもらっている江戸川乱歩に「何度でもやり直すんだ」と話すせりふがあることにも注目した。「今の私たちの状況にぴったり。主人公がそう叫ぶお芝居をみんなでつくろう」という成井の提案に賛同が集まった。
活気あふれる稽古場
稽古場は活気に満ちている。
「シーンの間の、台本に書いていない部分に何があるかは4回やってもやりつくすことができていません。新たな発見もあり意見を出し合っています」(成井、以下同)と議論も活発だ。
劇団初期は出入りが激しく、必ずしも愛着を持って入ってくる人が多いわけではなかったという。
「10年過ぎたあたりから、憧れてオーディションで入団する人が増えました。今回の公演の出演者のほとんどはファン出身。劇団に対する愛着があって彼らの熱さに驚かされます。自分がやっている時にこの劇団をつぶしたくないと強く思っているんだと思います」と裏打ちのある熱さに思いをいたす。
成井自身、「書いた時に考えていたことは覚えていない」ために台本には客観的になれ、作者というより演出家の目線になった。初演後の再演時以降はほとんどしないという書き換えにも取り組んだ。時代に合わない部分を修正したことで何かが吹っ切れ、大幅ではないが何度も書き換えたという。
劇団員の「自分たちでつくる」という意識の向上も感じる。「私は37年目で60歳、役者の主力メンバーは20年目ぐらいで40歳前後。年の差はありますが、対等に作品への意見を言ってもらえるので、36年やってきてよかったと感じています」と教え子たちの成長が頼もしそうでもある。
初演からは32年。登場人物のリアリティーには気を払う。「演劇のリアリティーはひとつだけある真実を追求するというより、時代の影響を受ける。私たちが演劇を始めた80年代のリアリティーって遊び心が大事で、生真面目にリアリティーを追求することを野田(秀樹)さんも鴻上(尚史)さんも否定したんじゃないでしょうか。私たちも役者が舞台上で躍動していればいいと思っていました」
だが演劇界では、90年代に「静かな演劇」が登場して現実感が重視され、2000年代にはアグレッシブな「劇団鹿殺し」のような流れと「ロロ」のような(ジャンル横断の)手法や「チェルフィッチュ」のようなアート系も登場した。「混沌としてきました。でも、私たちのやりたいお芝居におけるリアリティーは常に考えています。劇団だと役者たちと話し合って革新していけるんです」とあらためて劇団の良さに気付いている。
劇団公演の良さとは
一時的にとは言え劇団という場所を失った劇団員らは外部舞台や映像作品のほか、アルバイトで生活費を稼ぐ必要に迫られる人も。成井は演劇の指導やプロデュース公演の演出なども手掛けた。
休止1年後の昨年春から成井は呼び掛けを始め、今年12月に神戸と東京で舞台『サンタクロースが歌ってくれた』の上演が決まった。
成井がプロデュース公演の演出で感じたことが復活へ加速した大きな理由。「プロデュース公演をやればやるほど劇団公演の良さが身に染みるんです」と言う成井は「劇団員だといろいろ説明しなくても分かってくれるので、作業効率が非常に良い」と演出家ならではの理由を語る。
キャラメルボックスが拠点にしていたサンシャイン劇場(東京・池袋)のような約800人収容の劇場でのテンションの上げ方や、それを2階席の奥の観客にも分からせる全身での身体表現など、劇団員には何の説明もいらない。「プロデュース公演の俳優さんの中にはそれをオーバーアクトと感じる人もいるけど、劇団では稽古がどんどんと進む」のだという。
そのために「他の公演で初日に持っていくレベルに劇団では半分の日にちで到達する。そこからさらに工夫をして深掘りできる」と復活発表文に記した「キャラメルボックスでしかつくれないお芝居」の真意を語る。
※活動休止にいたる経緯や、2019年5月31日に活動休止を発表した後になにがあったのか、劇団員のその後、復活公演の見どころ、今後への思いなどについては2021年12月3日発売の『週刊金曜日』12月3日号に掲載される。
(阪清和・エンタメ批評家、2021年12月3日号より抜粋)